#
# 実は要訂正箇所を上記 Webサイト管理人に指摘した事が あるが、受け
# 現時点では恐らく上記 URI よりも本考察の方が詳しい上に正確と なっている ものと思われる
【三國志】 卷三十 魏志 烏丸鮮卑東夷傳 第三十 倭人傳
撰者 : 西晉(晋)朝 陳壽(寿)
倭人在帶方東南大海之中 依山㠀爲國邑 舊百餘國

# ()内の表音は私が無理矢理 片仮名で表したもので、権威あるセンセイ達が述べている表音では無い
| 字 | 字音候補 | 上古音 | 中古音 | 中世音 | 現代音 | 呉音 | 漢音 | 万葉仮名 | |
| 倭 | 一 | ・uar(ゥァ) | ・ua(ゥァ) | ・uo(ゥォ) | ・uə(ゥォ) | wō(ゥォ) | ワ | ワ | わ(日本書紀:歌謡) |
| 倭 | 二 | ・ɪuar(ゥィゥァ) | ・ɪuĕ(ゥィェ) | uəi(ゥェィ) | uəi(ゥェィ) | wēi(ゥェィ) | イ(ヰ) | イ(ヰ) | - |
| 倭 | 三 | - | - | - | - | wǒ(ゥォ) | - | - | - |
国名等が表れないので、進める漢時有朝見者 今使譯所通三十國
狗字 は他史書では別の字が用いられたりしていて、少々厄介で ある從郡至倭 循海岸水行 歴韓國 乍南乍東 到其北岸狗邪韓國 七千餘里
| 字 | 字音候補 | 上古音 | 中古音 | 中世音 | 現代音 | 拼音 | 呉音 | 漢音 | 万葉仮名 |
| 狗 | - | kug(ク) | kəu(コゥ) | kəu(コゥ) | kəu(コゥ) | gǒu(ゴォウ) | ク | コウ | 該当する表音無し |
| 拘 | 一 | kɪug(キゥ) | kɪu(キゥ) | kiu(キゥ) | ts̆ü(ツゥ) | jū(ジュー) | ク | ク | 該当する表音無し |
| 拘 | 二 | -(不明) | -(不明) | -(不明) | -(不明) | gōu(ゴウ) | ク | コウ | - |
| 邪 | 一 | ŋiăg(ンィァ) | (yiă)-ziă(ィァ-ジィァ) | sie(シェ) | s̆ie(シェ) | xié(シエェ) | ジャ | シャ | ざ(古事記:歌謡,万葉集) |
| 邪 | 二 | ŋiăg(ンィァ) | yiă(ィァ) | ie(イェ) | ie(イェ) | yé(イエ) | ヤ | ヤ | 該当する表音無し |
| 韓 | - | ɦan(ゥァン) | ɦan(ゥァン) | han(ハン) | han(ハン) | hán(ハッン) | カン | ガン | 該当する表音無し |
対海国に ついては以下でも触れているので、ここでは表音のみに始度一海千餘里 至對海國 其大官曰卑狗 副曰卑奴母離 所居絶島 方可四百餘里 土地山險 多深林 道路如禽鹿徑 有千餘戸 無良田 食海物自活 乘船南北市糴
| 字 | 字音候補 | 上古音 | 中古音 | 中世音 | 現代音 | 拼音 | 呉音 | 漢音 | 万葉仮名 |
| 對(対) | - | tuəd(トゥァドュ) | tuəi(トゥァィ) | tuəi(トゥァィ) | tuəi(トゥァィ) | duì(ドュイ) | タイ | タイ | 該当する表音無し |
| 海(海) | - | m̩əg(マ) | həi(ハイ) | hai(ハイ) | hai(ハイ) | hǎi(ハァ イ) | カイ | カイ | み甲類(日本書紀,古事記,万葉集)[註1] |
| 卑 | - | pieg(ピェ) | piĕ(ピェ) | pi(ピ) | pɔi(ピィ) | bēi(ベイ) | ヒ | ヒ | ひ甲類(日本書紀,古事記,万葉集) |
| 奴 | - | nag(ナ) | no(ndo)(ノ,ド) | nu(ヌ) | nu(ヌ) | nú(ヌゥ) | ヌ | ド | ど甲類(日本書紀:歌謡) ナ(日本書紀) ぬ(日本書紀,古事記,万葉集) の甲類(日本書紀,古事記) |
| 母 | - | muəg(ムォ) | məu(mbəu)(モゥ,ンボゥ) | mu(ム) | mu(ム) | mǔ(ム ゥ) | モ,ム | ボウ | も(日本書紀,万葉集) も乙類(古事記) |
| 離 | 一 | lɪar(リァ) | lɪĕ(リェ) | li(リ) | li(リ) | lí(リィイ) | リ | リ | り(日本書紀:歌謡) |
| 離 | 二 | - | - | - | - | lì(リイ) | ライ | レイ | 該当する表音無し |
万葉仮名では 海字 を み甲類 に分類するが、実際には
又南渡一海千餘里 名曰瀚海 至一大國 官亦曰卑狗 副曰卑奴母離 方可三百里 多竹木叢林 有三千許家差有田地 耕田猶不足食 亦南北市糴
| 字 | 字音候補 | 上古音 | 中古音 | 中世音 | 現代音 | 拼音 | 呉音 | 漢音 | 万葉仮名 |
| 瀚 | - | -(不明) | -(不明) | -(不明) | -(不明) | hán(ハッン) | ガン | カン | 該当する表音無し |
| 翰 | - | ɦan(ゥァン) | ɦan(ゥァン) | han(ハン) | han(ハン) | hán(ハッン) | ガン | カン | 該当する表音無し |
| 一 | - | ・iet(イェッ) | iĕt(イェッ) | iəi(イァィ) | i(イ) | yī(イ) | イチ | イツ | 該当する表音無し |
| 大 | 一 | dad(ダッ) | dai(ダイ) | tai(タイ) | tai(タイ) | dài(ダィ) | ダイ | タイ | 該当する表音無し |
| 大 | 二 | dar(ダァ) | da(ダ) | ta(タ) | ta(タ) | dà(ダァ) | ダ | タ | ダ(万葉集) ほ(日本書紀,古事記:歌謡) |
| 大 | 三 | -(不明) | -(不明) | -(不明) | -(不明) | tài(タィ) | タイ | タイ | 該当する表音無し |
・iet-dar(dad)(イッダッ) →ieti-da(イティダ) → ishi-da(イシュィダ) → isi-da(イシダ)
又渡一海千餘里 至末盧國 有四千餘戸 濱山海居 草木茂盛 行不見前人 好捕魚鰒 水無深淺 皆沈沒取之
| 字 | 字音候補 | 上古音 | 中古音 | 中世音 | 現代音 | 拼音 | 呉音 | 漢音 | 万葉仮名 |
| 末 | - | muat(ムァトゥ) | muat(mbuat)(ムァトゥ,ブァトゥ) | mo(モ) | mo(モ) | mò(モゥ) | マツ,マチ | バツ | ま(日本書紀:歌謡,万葉集) |
| 盧 | - | hlag-(hlo)(ラ,ロ) | (hlo)-lo(ロ) | lu(ル) | lu(ル) | lú(ルゥウ) | ル | ロ | る(日本書紀:歌謡) ろ甲類(日本書紀:歌謡,古事記:歌謡) |
東南陸行五百里 到伊都國 官曰爾支 副曰𣳘謨觚,柄渠觚 有千餘戸 世有王 皆統屬女王國 郡使往來常所駐

| 字 | 字音候補 | 上古音 | 中古音 | 中世音 | 現代音 | 拼音 | 呉音 | 漢音 | 万葉仮名 |
| 伊 | - | ・iə[breve][註2]r(イ) | ɪi(ィィ) | i(イ) | i(イ) | yī(イー) | イ | イ | い(日本書紀:歌謡,古事記:歌謡,万葉集) |
| 都(都) | - | tag(タ) | to(ト) | tu(トゥ) | tu(トゥ) | dū(ドゥ) | ツ | ト | つ(日本書紀:歌謡,古事記:歌謡,万葉集) づ(日本書紀:歌謡,万葉集) |
| 爾 | - | nier(ニェ) | niĕ(riĕ)(ニェ,リェ) | rɪ(リ) | rr(ル) | ĕr(ィィル) | ニ | ジ | に(日本書紀,古事記,万葉集) |
| 支 | - | kieg(キェ) | tʃɪĕ(シェ,チェ) | ṭṣï(ツィ) | ṭṣï(ツィ) | zhī(ジィ) | シ | シ | き甲類(古事記:歌謡,万葉集) ぎ甲類(万葉集) |
| 𣳘(泄) | 一 | siat(シァッ) | siɛt(シェッ) | sie(シエ) | s̆ie(シエ) | xiè(シエ) | セチ | セツ | 該当する表音無し |
| 𣳘(泄) | 二 | ḍiad(ディアッドゥ) | yiɛi(ィェィ) | iəi(ィェィ) | i(イ) | yì(イ) | エ | エイ | 該当する表音無し |
| 謨 | - | mag(マ) | mo(mbo)(モ,ンボ) | -(不明) | -(不明) | mó(モ ォ) | モ | ボ | も(日本書紀:歌謡) |
| 觚 | - | kuag(クァ) | ko(コ) | ku(ク) | ku(ク) | gū(グー) | ク | コ | 該当する表音無し |
| 柄 | - | pɪăŋ(ピァン) | pɪʌŋ(ピァン) | piəŋ(ピァン) | piəŋ(ピァン) | bǐng(ビィン) | ヒョウ(ヒヤウ) | ヘイ | 𛀁(万葉集)[註3] |
| 渠 | 一 | gɪag(ギァ) | gɪo(ギォ) | kʻio(ク ィオ) | ts̆ʻü(ツィ) | qú(チー) | ゴ | キョ | こ乙類(日本書紀:歌謡) ご乙類(日本書紀:歌謡) |
| 渠 | 二 | - | - | - | - | jù(ヂゥ) | - | - | - |
ə の上に ˘(
万葉仮名では や行音4段音の ![]() に分類されるが、これは訓読み のため漢語表音と関連が あるか は不明
に分類されるが、これは訓読み のため漢語表音と関連が あるか は不明
𛀁 に ついては以下を参照
や行え - Wikipedia
東南至奴國百里 官曰兕馬觚 副曰卑奴母離 有二萬餘戸
| 字 | 字音候補 | 上古音 | 中古音 | 中世音 | 現代音 | 拼音 | 呉音 | 漢音 | 万葉仮名 |
| 兕 | - | -(不明) | zii(ジィ) | sï(シ) | sï(シ) | sì(シッ) | ジ | シ | 該当する表音無し |
| 馬 | - | măg(マァ) | mă(mbă)(マァ,ンバァ) | mag(マ) | mag(マ) | mă(マァ) | メ | バ | ま(日本書紀[註4],古事記,万葉集) メ甲類(日本書紀[註5],万葉集) バ(日本書紀)[註6] |
但馬國 と あるので、厳密には万葉仮名とは言えないか
鞍部村主司馬達等 と あるので、厳密には万葉仮名とは言えないかも知れない
熊山縣令,上柱國 司馬法聰 等 と あり、厳密には万葉仮名では無い
東行至不彌國百里 官曰多模 副曰卑奴母離 有千餘家
| 字 | 字音候補 | 上古音 | 中古音 | 中世音 | 現代音 | 拼音 | 呉音 | 漢音 | 万葉仮名 |
| 不 | 一 | pɪuət(ピゥォッ) | pɪuət(ピゥォッ) | pu(プ) | pu(プ) | bù(ブウ) | ホチ | フツ | - |
| 不 | 二 | pɪuəg(ピゥォ) | pɪəu(ピォゥ) | fəu(フォゥ) | fəu(フォゥ) | fǒu(フォ ウ) | フ | フウ | ふ(日本書紀,万葉集) ぶ(万葉集) |
| 不 | 三 | - | - | - | - | fū(フゥ) | フ | フ | - |
| 彌(弥) | 一 | miĕr(ミェ) | miĕ(mbiĕ)(ミェ,ムビェ) | mi(ミ) | mi(ミ) | mí(ミイ) | ミ | ビ | み甲類(日本書紀:歌謡,古事記:歌謡,万葉集) ム(日本書紀)[註7] び甲類(日本書紀:歌謡) |
| 彌(弥) | 二 | - | - | - | - | mǐ(ミ ィ) | ミ | ビ | - |
| 多 | - | tar(タ) | ta(タ) | tuo(トゥォ) | tuə(トゥォ) | duō(ドゥォ) | タ | タ | た(日本書紀:歌謡,古事記:歌謡,万葉集) だ(日本書紀:歌謡,古事記:歌謡,万葉集) |
| 模 | - | mag(マ) | mo(mbo)(モ,ンボ) | mu(ム) | mu(ム) | mó(モ) | モ | ボ | む(万葉集)[註8] も(日本書紀:歌謡) |
屠南蠻 忱彌多禮 と あり、厳密には万葉仮名では無い
南至投馬國水行二十日 官曰彌彌 副曰彌彌那利 可五萬餘戸
| 字 | 字音候補 | 上古音 | 中古音 | 中世音 | 現代音 | 拼音 | 呉音 | 漢音 | 万葉仮名 |
| 投 | - | dug(ドゥ) | dəu(ドゥ) | tʻəu(トウ) | tʻəu(トウ) | tóu(トウ) | ズ(ヅ) | トウ | 該当する表音無し |
| 那 | 一 | nar(ナ) | na(nda)(ナ,ンダ) | na(ナ) | na(ナ) | nă(ナ ァ) | ナ | ダ | な(日本書紀,古事記:歌謡,万葉集) |
| 那 | 二 | - | - | - | - | nuó(ヌォ) | ナ | ダ | - |
| 利 | - | lɪed(リェ) | lɪi(リィ) | li(リ) | li(リ) | lì(リー) | リ | リ | と甲類(万葉集) ど甲類(万葉集) り(日本書紀:歌謡,万葉集) |
南至邪馬壹國 女王之所都 水行十日 陸行一月 官有伊支馬 次曰彌馬升 次曰彌馬獲支 次曰奴佳鞮 可七萬餘戸
| 字 | 字音候補 | 上古音 | 中古音 | 中世音 | 現代音 | 拼音 | 呉音 | 漢音 | 万葉仮名 |
| 壹(壱) | 一 | ・iet(ィェッ) | iĕt(イェッ) | iəi(イァィ) | i(イ) | yī(イー) | イチ | イツ | イチ(万葉集) |
| 壹(壱) | 二 | - | - | - | - | yīn(イン) | - | - | - |
| 臺 | - | dəg(ダ) | dəi(ダイ) | t'ai(タイ) | t'ai(タイ) | - | ダイ | タイ | 該当する表音無し |
| 台 | 一 | t'əg(タ) | t'əi(タイ) | t'ai(タイ) | t'ai(タイ) | tái(タイ) | ダイ | タイ | と乙類(日本書紀) |
| 台 | 二 | d̩iəg(ディェ) | yiei(ィェィ) | i(イ) | i(イ) | yí(イ) | イ | イ | 該当する表音無し |
| 升 | - | thiəŋ(シァン) | ʃɪəŋ(シァン) | ʃɪəŋ(シァン) | ṣəŋ(シァン) | shēng(シァン) | ショウ | ショウ | 該当する表音無し |
| 獲 | - | ɦuăk(ゥァック) | ɦuɛk(ゥェック) | huo(フオ) | huə(フオ) | huò(フオォ) | ワク | カク(クワク) | 該当する表音無し |
| 佳 | - | kĕg(ケ) | kăi(カイ) | kiai(キァィ) | ts̆ia(ツィア) | jiā(ジアー) | ケ | カイ | 該当する表音無し |
| 鞮 | - | -(不明) | -(不明) | -(不明) | -(不明) | dī(ディ) | タイ | テイ | 該当する表音無し |
国名が連続して表れるが、どれが どこか判然と しない自女王國以北 其戸數,道里可得略載 其餘旁國遠絶 不可得詳
次有斯馬國 次有已百支國 次有伊邪國 次有郡支國 次有彌奴國 次有好古都國 次有不呼國 次有姐奴國 次有對蘇國 次有蘇奴國 次有呼邑國 次有華奴蘇奴國 次有鬼國 次有爲吾國 次有鬼奴國 次有邪馬國 次有躬臣國 次有巴利國 次有支惟國 次有烏奴國 次有奴國 此女王境界所盡
| 字 | 字音候補 | 上古音 | 中古音 | 中世音 | 現代音 | 拼音 | 呉音 | 漢音 | 万葉仮名 |
| 斯 | - | sieg(シエ) | siĕ(シエェ) | sï(シィ) | sï(シィ) | sī(シー) | シ | シ | し(日本書紀:歌謡,古事記:歌謡,万葉集) |
| 已 | - | d̩iəg(ディェ) | yiei(ィェィ) | i(イ) | i(イ) | yǐ(ィーィ) | イ | イ | い(万葉集) |
| 百 | 一 | păk(パァク) | pʌk(パク) | pai(パイ) | pai(パイ) | băi(バァイ) | ヒャク | ハク | ほ(日本書紀,古事記,万葉集) |
| 百 | 二 | păk(パァク) | pʌk(パク) | po(ポ) | po(ポ) | bó(ボォ) | - | - | - |
| 郡 | - | gɪuən(グィン) | gɪuən(グィン) | kɪuən(クィン) | ts̆üən(ツィン) | jùn(ヂュィン) | グン | クン | 該当する表音無し |
| 好 | 一 | hog(ホ) | hau(ハゥ) | hau(ハゥ) | hau(ハゥ) | hào(ハォ) | コウ(カウ) | コウ(カウ) | よ乙類[註9](万葉集) |
| 好 | 二 | - | - | - | - | hăo(ハァオ) | コウ(カウ) | コウ(カウ) | - |
| 古 | - | kag(カ) | ko(コ) | ku(ク) | ku(ク) | gǔ(グ ゥ) | ク | コ | こ甲類(日本書紀:歌謡,古事記:歌謡,万葉集) |
| 姐 | 一 | tsiăg(ツィァ) | tsiă(ツィァ) | tsie(ツィェ) | ts̆ie(ツィェ) | jiĕ(ヂエェ) | シャ | シャ | 該当する表音無し |
| 姐 | 二 | - | - | - | - | jù(ヂイ) | ソ | ショ | - |
| 蘇 | - | sag(サ) | so(ソ) | su(ス) | su(ス) | sū(スゥ) | ス | ソ | そ甲類(日本書紀:歌謡,古事記:歌謡,万葉集) |
| 呼 | - | hag(ハ) | ho(ホ) | hu(フ) | hu(フ) | hū(フゥ) | ク | コ | を(万葉集) |
| 邑 | - | ・ɪəp(ィァプ) | ・ɪəp(ィァプ) | iəi(ィァィ) | i(イ) | yì(イィ) | オウ(オフ) | イウ(イフ) | 該当する表音無し |
| 華 | 一 | - | - | - | - | huā(フア) | ケ(クヱ) | カ(クワ) | 該当する表音無し |
| 華 | 二 | ɦuăg(ゥァァ) | ɦuă(ゥァァ) | huă(フアァ) | huă(フアァ) | huá(フ ァア) | ゲ(ゲヱ) | カ(クワ) | 該当する表音無し |
| 華 | 三 | - | - | - | - | huà(フアァ) | ゲ(ゲヱ) | カ(クワ) | 該当する表音無し |
| 爲(為) | 一 | ɦɪuar(ィゥァ) | ɦɪuĕ(ィゥェ) | uəi(ゥェィ) | uəi(ゥェィ) | wéi(ゥェィ) | イ(ヰ) | イ(ヰ) | し(万葉集)[註9] す(万葉集)[註9] せ(万葉集)[註9] は(万葉集)[註9] ゐ(万葉集) を(万葉集) |
| 爲(為) | 二 | - | - | - | - | wèi(ゥエィ) | イ(ヰ) | イ(ヰ) | - |
| 躬 | - | kɪoŋ(キォン) | kɪuŋ(キゥン) | kioŋ(キォン) | kuəŋ(クォン) | gōng(ゴン) | ク,クウ | キュウ | み乙類(日本書紀)[註10] |
| 臣 | - | ghien(ギェン) | ʒɪĕn(ジエン) | tʃʻɪeŋ(チエン) | ṭṣʻən(チェン) | chén(チェン) | ジン | シン | み甲類[註10] |
| 巴 | - | păg(パ) | pă(パァ) | pa(パ) | pa(パ) | bā(バ) | ヘ | ハ | は(日本書紀) |
| 惟 | - | ḍiuə[breve][註2]r(ディゥァ) | yiui(ィゥィ) | uəi(ゥェィ) | uəi(ゥェィ) | wéi(ウェイ) | イ(ヰ) | ユイ | 該当する表音無し |
| 烏 | - | ・ag(ゥァ) | ・o(ォ) | u(ウ) | u(ウ) | wū(ウー) | ウ | オ(ヲ) | い(日本書紀)[註11] う(日本書紀[註12],万葉集) |
表音とは何の関係も無く ただ 万葉集 に借訓文字として使用されているので、厳密には万葉仮名と言って良いのかは何とも言えない
借訓文字
借訓文字か
万葉仮名では ないのかも知れない
智字 は何故 知字 を用いないので あろうか?其南有狗奴國 男子爲王 其官有狗古智卑狗 不屬女王
| 字 | 字音候補 | 上古音 | 中古音 | 中世音 | 現代音 | 拼音 | 呉音 | 漢音 | 万葉仮名 |
| 智 | - | tɪeg(ティェ) | ṭɪĕ(ティェ) | ṭṣï(シィ) | ṭṣï(シィ) | zhì(ジー) | チ | チ | ち(日本書紀:歌謡,万葉集) |
# 例えば井上 光貞『日本の歴史 1 神話から歴史へ』(中公文庫、一九七三年)
自郡至女王國萬二千餘里
男子無大小皆黥面文身
自古以來 其使詣中國 皆自稱大夫
夏后少康之子封於會𥡴 斷髮丈[註13]身 以避蛟龍之害
今倭水人好沈沒捕魚蛤 丈[註13]身亦以厭大魚水禽 後稍以爲飾
諸國文身各異 或左或右 或大或小 尊卑有差

註13:計其道里 當在會𥡴東治之東
其風俗不淫 男子皆露紒 以木緜招頭其衣横幅 但結束相連 略無縫
婦人被髮屈紒 作衣如單被 穿其中央 貫頭衣之
種禾稻,紵麻 蠶桑 緝績 出細紵,縑緜
其地無牛,馬,虎,豹,羊,鵲
兵用矛,楯,木弓 木弓短下長上 竹箭或鐵鏃或骨鏃
所有無與儋耳,朱崖同
倭地温暖 冬夏食生菜 皆徒跣
有屋室 父,母,兄,弟臥息異處
以朱丹塗其身體 如中國用粉也
食飮用籩豆 手食
其死 有棺無槨 封土作冢
始死停喪十餘日 當時不食肉 喪主哭泣 他人就歌舞飮酒
已葬 舉家詣水中澡浴 以如練沐
文字 の誤か
| 字 | 字音候補 | 上古音 | 中古音 | 中世音 | 現代音 | 拼音 | 呉音 | 漢音 | 万葉仮名 |
| 少 | 一 | thiɔg(ショウ) | ʃɪɛu(シェウ) | ʃɪeu(シェウ) | ṣau(シャウ) | shăo(シャ オ) | ショウ(セウ) | ショウ(セウ) | 該当する表音無し |
| 少 | 二 | - | - | - | - | shào(シャオ) | - | - | - |
| 康 | - | kʻaŋ(カァン) | kʻaŋ(カァン) | kʻaŋ(カァン) | kʻaŋ(カァン) | kāng(カァン) | コウ(カウ) | コウ(カウ) | 該当する表音無し |
| 儋 | - | tam(タム) | tam(タム) | tam(タム) | tan(タム) | dān(ダァン) | タン(タム) | タン(タム) | 該当する表音無し |
| 耳 | 一 | niəg(ニェ) | niei(rɪei)(ニェィ,リェィ) | rɪ(リ) | rr(ル) | ĕr(ウゥル) | ニ | ジ | じ(日本書紀:歌謡) に(万葉集) みみ(日本書紀)[註14] |
| 耳 | 二 | - | - | - | - | réng(レン) | ニョウ | ジョウ | 該当する表音無し |
| 朱 | - | tiug(ティゥ) | tʃɪu(チゥ) | tʃɪu(チゥ) | ṭṣu(スゥ) | zhū(ヂゥ) | ス | シュ | 該当する表音無し |
| 崖 | - | ŋĕg(ンゥェ) | ŋăi(ンァィ) | iai(ィァィ) | iai(ィァィ) | yái(yá)(ヤ イ,ヤァ) | ゲ | ガイ | 該当する表音無し |
みみ は人名に当てられているので、厳密に言えば借訓万葉仮名
持衰 とは漢語で あろうか、それとも倭語で あろうか其行來渡海詣中國 恆使一人
不梳頭 不去蟣蝨 衣服垢汚 不食肉 不近婦人 如喪人 名之爲持衰
# 漢文訓読では 衰絰 の語彙は すいてつ では無く さいてつ と
【史記】 卷五 秦本紀第五
撰者 : 西漢朝 司馬 遷
夷吾姊亦為繆公夫人 夫人聞之 乃衰[註15]絰跣曰
妾兄弟不䏻[註16]相救 以辱君命

影本画像には 衰字 の異体字 ![]() で書かれている
で書かれている
厳密に言えば影本の異体字は鍋蓋(亠) の下の横線が一本少ない 龷 と なっている
能字 の異体字で あるが、影本を見るに正確には ![]()
【史記】 卷五 秦本紀第五
太子襄公怒曰
秦侮我孤 因喪破我滑
遂墨衰絰 𤼲[註17]兵遮[註18]秦兵於殽[註19]擊之 大破秦軍無一人得脫者

𤼲字 の異体字で あるが、正確には ![]()
遮字 の異体字 ![]()
影本画像は 殽字 の異体字か 肴の上は 㐅 ではなく 又
【史記】 卷五 秦本紀第五
韓王衰絰入吊[註20]祠[註21] 諸侯[註22]皆使其将相来吊[註20]祠[註21] 視喪事
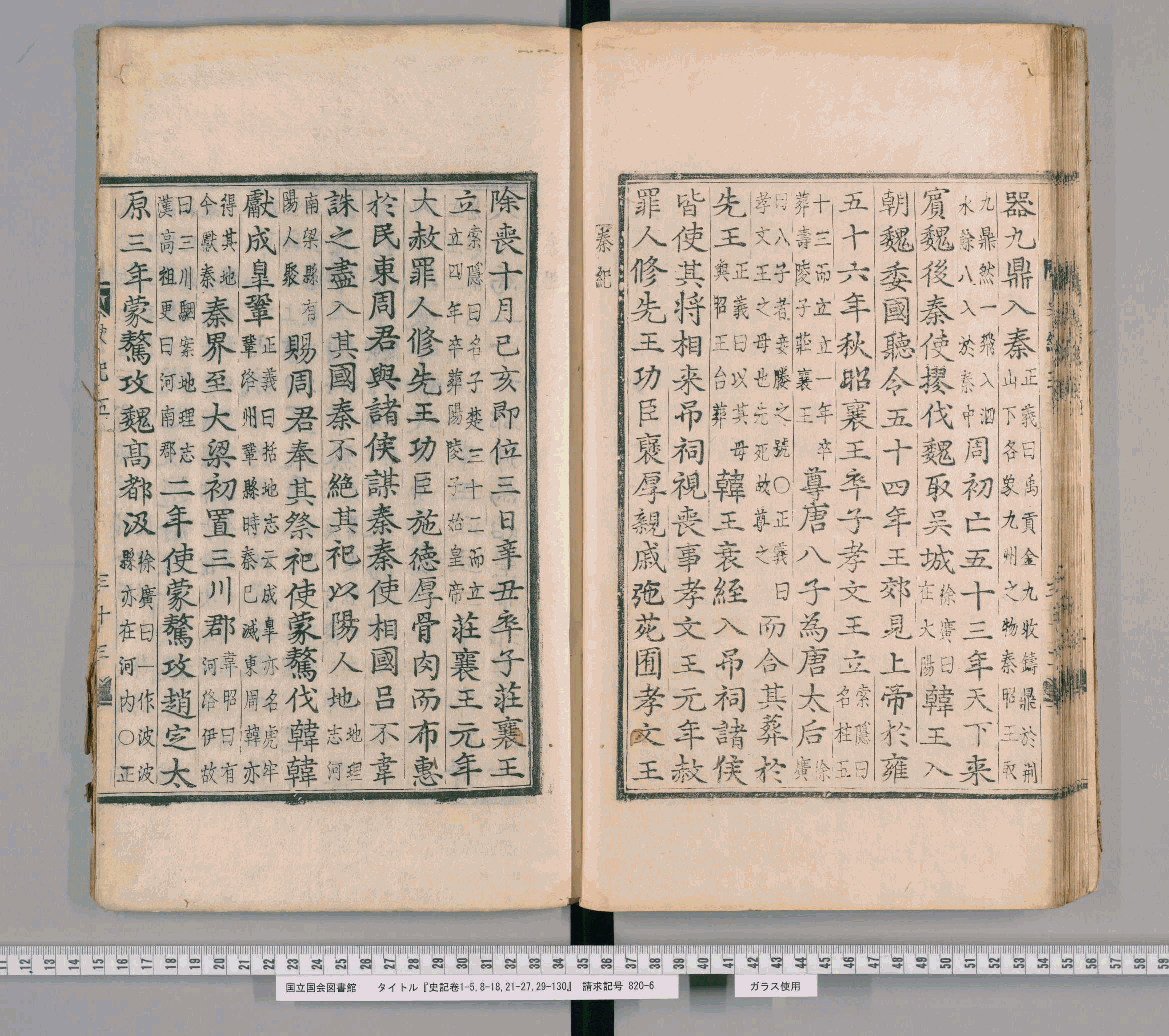
吊字 は 弔字 の異体字として書かれている
影本画像では ![]() と書かれている
と書かれている
影本画像では
| 字 | 字音候補 | 上古音 | 中古音 | 中世音 | 現代音 | 拼音 | 呉音 | 漢音 | 万葉仮名 |
| 持 | - | dɪəg(ディェ) | ḍɪei(ディェィ) | ṭṣʻï(シィ) | ṭṣʻï(シィ) | chí(チイ) | ジ(ヂ) | チ | 該当する表音無し |
| 衰 | 音一 | sïuər(シゥァ) | ṣïuei(シゥェィ) | ṣuəi(スァィ) | ṣuai(スァィ) | shuāi(シュアイ) | スイ | スイ | 該当する表音無し |
| 衰 | 音二 | tsʻïuər(シァ) | ṭṣʻïuĕ(シゥェ) | ṭṣʻuəi(スァィ) | ṭṣʻuai(スァィ) | - | シ | シ | - |
| 衰 | 音三 | tsʻuər(ツゥェ) | tsʻuəi(ツゥェィ) | tsʻuəi(ツゥェィ) | tsʻuəi(ツゥェィ) | cuī(ツゥイ,ツゥェイ) | セ | サイ | - |
註23:若行者吉善 共顧其生口,財物 若有疾病 遭暴害 便欲殺之謂其持衰不謹
出真珠,青玉 其山有丹 其木有柟,杼,豫樟,楙櫪,投橿,烏號,楓香
其竹篠,簳,桃支 有薑,橘,椒,蘘荷 不知以爲滋味 有獮猴,黒雉
其俗舉事行來 有所云爲 輒灼骨而卜 以占吉凶 先告所卜 其辭如令龜法 視火坼占兆
其會同坐起 父子男女無別 人性嗜酒魏略曰 其俗不知正歳[註23]四節 但計春耕秋收爲年紀
見大人所敬 但搏手以當跪拜
其人壽考 或百年 或八,九十年
其俗 國大人皆四,五婦 下戸或二,三婦
婦人不淫 不妒忌
不盜竊 少諍訟 其犯法 輕者没其妻子 重者没其門戸及宗族
尊卑各有差序 足相臣服
収租賦有邸閣 國國有市交易有無 使大倭[註24]監之
自女王國以北 特置一大率 檢察諸國畏憚之 常治伊都國 於國中有如刺史
王遣使詣京都,帶方郡 諸韓國及郡使倭國 皆臨津搜露 傳送文書,賜遺之物詣女王 不得差錯
歳字 は 嵗字 が正しいか
しかし影本画像を見るに旁の 少字 は 小字 に見えるので、厳密に言えば どちらでも無い
使大倭 が官号で 使大倭 之を監す と読むべきか、大倭 が官号で 大倭を
| 字 | 字音候補 | 上古音 | 中古音 | 中世音 | 現代音 | 拼音 | 呉音 | 漢音 | 万葉仮名 |
| 使 | 音一 | sïəg(シ ェ) | ṣïei(シ ェィ) | ṣï(シ) | ṣï(シ) | shǐ(シ イ) | シ | シ | 該当する表音無し |
| 使 | 音二 | - | - | - | - | shì(シィ) | - | - | - |
| 率 | 音一 | lɪət(リェッ) | lɪĕt(リェッ) | liu(リゥ) | lü(ルゥ) | lù(ルゥ) | リチ | リツ | 該当する表音無し |
| 率 | 音二 | sïuət(シゥェッ) | ṣïuĕt(シゥェッ) | ṣui(シュィ) | ṣuai(シュァィ) | shuài(シュァィ) | ソチ,シュチ | ソツ | ゐ(万葉集)[註25] |
| 率 | 音三 | sïuəd(シゥェッ) | ṣïui(シゥィ) | ṣuai(シュァィ) | ṣuai(シュァィ) | shuài(シュァィ) | スイ | スイ | 該当する表音無し |
敢えて言えば借訓の万葉仮名と言う事に なる
噫 の表音は倭語を聞いた上で同音の漢字を当てたものと思われるが、この字の発音は非常に難しい下戸與大人相逢道路 逡巡入草 傳辭説事 或蹲或跪 兩手據地 爲之恭敬對應聲曰噫 比如然諾
| 字 | 字音候補 | 上古音 | 中古音 | 中世音 | 現代音 | 拼音 | 呉音 | 漢音 | 万葉仮名 |
| 噫 | 音一 | ・ɪəg(ィァ) | ɪei(ィェイ) | i(イ) | i(イ) | yī(イー) | イ | イ | 該当する表音無し |
| 噫 | 音二 | ・ĕg(ゥグッ) | ʌi(アイ) | ai(アイ) | ai(アイ) | ài(アイ) | エ | アイ | 該当する表音無し |
| 噫 | 音三 | - | - | - | - | yì(イ) | オク | ヨク | - |
国名等が表れないので、進める其國本亦以男子爲王 住七,八十年 倭國亂 相攻伐歴年
卑弥呼 の中古音は ピミホ と読みたいが、当時の倭語ではハ行音が存在したか どうか乃共立一女子爲王 名曰卑彌呼 事鬼道 能惑衆 年已長大 無夫壻 有男弟 佐治國
【三國志】 卷四 魏志 三少帝紀 第四 齊王芳と言う訳で、漢和大字典で 俾 字を調べて見た
(正始四年)(243年)冬十二月 倭國女王俾彌呼 遣使奉獻
| 字 | 字音候補 | 上古音 | 中古音 | 中世音 | 現代音 | 拼音 | 呉音 | 漢音 | 万葉仮名 |
| 俾 | 音一 | pieg(ピェ) | piĕ(ピェ) | pi(ピ) | pi(ピ) | bǐ(ビ イ) | ヒ | ヒ | 該当する表音無し |
| 俾 | 音二 | - | - | - | - | bì(ビィ) | ビ | ヒ | - |
| 俾 | 音三 | pʻeg(ペ) | pʻei(ペイ) | pʻiəi(ピァィ) | pʻi(ピ) | pì(ピィ) | ハイ | ヘイ | 該当する表音無し |
国名等が表れないので、進める自爲王以來 少有見者 以婢千人自侍 唯有男子一人給飮食 傳辭出入
居處宮室樓觀 城柵嚴設 常有人持兵守衞
女王國東渡海千餘里 復有國 皆倭種
侏儒国に裸国そして黒歯国は漢語で あろうが、一応 掲げておく又有侏儒國在其南 人長三,四尺 去女王四千餘里
又有裸國,黒齒國 復在其東南 船行一年可至
| 字 | 字音候補 | 上古音 | 中古音 | 中世音 | 現代音 | 拼音 | 呉音 | 漢音 | 万葉仮名 |
| 侏 | - | tiug(ティゥ) | tʃɪu(シゥ) | tʃɪu(シゥ) | ṭṣu(ツゥ) | zhū(ヂゥ) | ス | シュ | 該当する表音無し |
| 儒 | - | niug(ニゥ) | niu(rɪu)(ニゥ,リゥ) | rɪu(リゥ) | ru(ルゥ) | rú(ルゥ) | ニュウ | ジュ | ず(日本書紀:歌謡) ぬ(日本書紀) |
| 裸 | - | luar(ルア) | lua(ルア) | luo(ルオ) | luə(ルオ) | luǒ(ルオォ) | ラ | ラ | 該当する表音無し |
| 黒 | 音一 | m̥ək(メク) | hək(ヘク) | həi(ヘイ) | həi(ヘイ) | hēi(ヘイ) | コク | コク | 該当する表音無し |
| 黒 | 音二 | m̥ək(メク) | hək(ヘク) | hə(ヘ) | hə(ヘ) | - | - | - | - |
| 齒(歯) | - | tʻ[註26]iag(トィァ) | tʃʻɪrei(ツィレィ) | ṭṣʻi(シィ) | ṭṣʻi(シィ) | chǐ(チィー) | シ | シ | シ(万葉集)[註27] は(古事記,日本書紀)[註28] ば(万葉集)[註28] よ乙類(万葉集)[註29] |
この発音記号は 1979年に廃止された らしい
万葉仮名と見做して良いのか どうか
借訓の万葉仮名
かなり乱れた使用例で あり、これを万葉仮名と認めるには疑念が残る
私見では歌者もしくは録者の漢字知識が不充分で あるための誤用では ないか と考える
国名等が表れないので、進める參問倭地 絶在海中洲㠀之上 或絶或連 周旋可五千餘里
景初二年 六月 倭女王遣大夫難升米等詣郡 求詣天子朝獻 太守劉夏遣吏將送詣京都
| 字 | 字音候補 | 上古音 | 中古音 | 中世音 | 現代音 | 拼音 | 呉音 | 漢音 | 万葉仮名 |
| 難(難) | 音一 | nan(ナン) | nan(ndan)(ナン,ダン) | nan(ナン) | nan(ナン) | nàn(ナン) | ナン | ダン | な(日本書紀,万葉集) |
| 難(難) | 音二 | - | - | - | - | nán(ナン) | ナン | ダン | - |
| 難(難) | 音三 | - | - | - | - | nuó(ヌオ) | ナ | ダ | - |
| 米 | - | mer(メ) | mei(mbei)(メイ,ベイ) | miəi(ミィ) | mi(ミ) | mǐ(ミ ィ) | マイ | ベイ | め乙類(日本書紀,古事記,万葉集) |
其年 十二月 詔書報倭女王曰
制詔親魏倭王卑彌呼 帶方太守劉夏遣使送汝大夫難升米 次使都市牛利奉汝所獻 男生口四人 女生口六人 班布二匹二丈 以到 汝所在踰遠 乃遣使貢獻 是汝之忠孝 我甚哀汝 今以汝爲親魏倭王 假金印紫綬 裝封付帶方太守假授汝 其綏撫種人 勉爲孝順
汝來使難升米,牛利渉遠 道路勤勞
| 字 | 字音候補 | 上古音 | 中古音 | 中世音 | 現代音 | 拼音 | 呉音 | 漢音 | 万葉仮名 |
| 市 | - | dhiəg(ディェ) | ʒɪei(ジエィ) | ṣï(シー) | ṣï(シー) | shì(シー) | ジ | シ | し(日本書紀,万葉集) ち(日本書紀,古事記,万葉集) |
| 牛 | - | ŋɪog(ンギォ) | ŋɪəu(ンギゥ) | niəu(ニゥ) | niəu(ニゥ) | niú(ニゥ) | グ | ギュウ(ギウ) | し(日本書紀)[註30] |
国名等が表れないので、進める今以難升米爲率善中郎將 牛利爲率善校尉 假銀印靑綬 引見勞賜遣還
今以絳地交龍錦五匹臣松之以爲 地應爲綈 漢文帝著皂衣 謂之戈綈是也 此字不體 非魏朝之失 則傳冩者誤也 絳地縐粟罽十張 蒨絳五十匹 紺青五十匹 荅汝所獻貢直
又特賜汝 紺地句文錦三匹 細班華罽五張 白絹五十匹 金八兩 五尺刀二口 銅鏡百枚 真珠,鉛丹各五十斤
皆裝封付難升米,牛利還到録受 悉可以示汝國中人 使知國家哀汝 故鄭重賜汝好物也
正始元年 太守弓遵遣建中校尉梯儁等 奉詔書,印綬詣倭國 拜假倭王 并齎詔 賜金,帛,錦罽,刀,鏡,采物
倭王因使上表荅謝恩詔
其四年 倭王復遣使大夫伊聲耆,掖邪拘等八人 上獻生口,倭錦,絳靑縑,緜衣,帛布,丹木,𤝔,短弓矢
掖邪狗等壹拜率善中郎將印綬
| 字 | 字音候補 | 上古音 | 中古音 | 中世音 | 現代音 | 拼音 | 呉音 | 漢音 | 万葉仮名 |
| 聲(声) | - | thieŋ(シェン) | ʃɪɛŋ(シェン) | ʃɪəŋ(シァン) | ṣəŋ(シァン) | shēng(シァン) | ショウ(シヤウ) | セイ | と乙類(万葉集)[註31] な(日本書紀)[註32] ね(日本書紀)[註33] |
| 耆 | 音一 | gier(ギェ) | gii(ギィ) | kʻi(キィ) | kʻs̆i(キィ) | qí(チィー) | ギ | キ | き甲類(日本書紀) ぎ類(日本書紀) |
| 耆 | 音二 | dhier(ディェ) | ʒɪi(ジィ) | ṣï(シィ) | ṣï(シィ) | shì(シィ) | シ | シ | 該当する表音無し |
| 耆 | 音三 | - | - | - | - | zhǐ(ヂ ィ) | - | - | 該当する表音無し |
| 掖 | - | d̩iak(ディァック) | yiɛk(ィェック) | iəi(イィ) | i(イ) | yè(イエ) | ヤク | エキ | 該当する表音無し |
何故 と乙類 として訓まれているのか、私には分からぬ
借訓の万葉仮名か
借訓の万葉仮名
其六年 詔賜倭難升米黃幢 付郡假授
其八年 太守王頎到官
倭女王卑彌呼與狗奴國男王卑彌弓呼素不和 遣倭載斯烏越等詣郡 説相攻擊狀
| 字 | 字音候補 | 上古音 | 中古音 | 中世音 | 現代音 | 拼音 | 呉音 | 漢音 | 万葉仮名 |
| 弓 | - | kɪuəŋ(キゥン) | kɪuŋ(キゥン) | kɪoŋ(キォン) | kuəŋ(クォン) | gōng(ゴォン) | ク・クウ | キュウ(キウ) | ゆ(日本書紀,古事記,万葉集)[註34] |
| 載 | 音一 | tsəg(ツァ) | tsəi(ツァィ) | tsai(ツァィ) | tsai(ツァィ) | zài(ヅァィ) | ザイ・サイ | サイ | 該当する表音無し |
| 載 | 音二 | - | - | - | - | zăi(ヅァ ィ) | サイ | サイ | - |
| 越 | - | ɦɪuăt(ウィゥァッ) | ɦɪuʌt(ウィゥァッ) | iue(イゥェ) | üe(ウェ) | yuè(ユェ) | オチ(ヲチ)・エチ(ヱチ) | エツ(ヱツ) | を(万葉集) |
借訓の万葉仮名
国名等が表れないので、進める遣塞曹掾史張政等因齎詔書,黄憧 拜假難升米爲檄告喻之
卑彌呼以死 大作冢 徑百餘歩 徇葬者奴婢百餘人
更立男王 國中不服 更相誅殺 當時殺千餘人
復立卑彌呼宗女壹與 年十三爲王 國中遂定
政等以檄告喻壹與
壹與遣倭大夫率善中郎將掖邪狗等二十人送政等還 因詣臺獻上男女生口三十人 貢白珠五千孔,靑大句珠二枚,異文雜錦二十匹
| 字 | 字音候補 | 上古音 | 中古音 | 中世音 | 現代音 | 拼音 | 呉音 | 漢音 | 万葉仮名 |
| 與(与) | 音一 | ɦiag(ɦio)(ィァ,ィォ) | (ɦio)yio(ィォ,ィョ) | iu(ィゥ) | ü(ュゥ) | yǔ(ュ ィ) | ヨ | ヨ | こ乙類(万葉集)[註35] と乙類(日本書紀,古事記,万葉集)[註36] よ乙類(日本書紀,古事記,万葉集) |
| 與(与) | 音二 | - | - | - | - | yú(ュィ) | - | - | - |
| 與(与) | 音三 | - | - | - | - | yù(イィ) | - | - | - |
かなり特殊な用例に思える
借訓の万葉仮名
| 名称 | 上古音 | 中古音 | 一般的な日本語表音 |
| 対海国 | tuəd-m̩əg(トゥァドュマ) | tuəi-həi(トゥァィハイ) | つしま国/タイカイ国 |
| 対馬国 | tuəd-măg(トゥァマァ) | tuəi-mă(mbă)(トゥァィマァ) | つしま国 |
| 一大国 | ・iet-dar(dad)(イッダッ) | iĕt-da(dai)(イッダイ) | イキ国/イチダイ国 |
| 一支国 | ・iet-kieg(イッキェ) | iĕt-tʃɪĕ(イッシェ,イッチェ) | イキ国 |
| 末盧国 | muat-hlag(ムァトゥラ) | muat(mbuat)-lo(hlo)(ムァトゥロ) | マツロ国 |
| 名称 | 上古音 | 中古音 | 一般的な日本語表音 |
| 伊都国 | ・iə[breve]r-tag(イタ) | ɪi-to(ィィト) | イト国 |
| 狗古智卑狗 | kug-kag-tɪeg-pieg-kug(クカティピク) | kəu-ko-ṭɪĕ-piĕ-kəu(コゥコティピコゥ) | くこちひく,ここちひこ |
| 卑弥呼 | pieg-miĕr-hag(ピェミェハ) | piĕ-miĕ-ho(ピェミェホ) | ひみこ |
| 都市牛利 | tag-dhiəg-ŋɪog-lɪed(タディェンギォリェ) | to-zɪei-ŋɪəu-lɪi(トジエィンギゥリィ) | としごり/トシギュウリ |
| 卑弥弓呼 | pieg-miĕr-kɪuəŋ-hag(ピェミェキゥンハ) | piĕ-miĕ-kɪuŋ-ho(ピェミェキゥンホ) | ひみくこ,ひみここ,ひみきゅうこ |
| 壱与 | ・iet-ɦiag(ɦio)(イッヤ/イッヨ) | iĕt-(ɦio)yio(イッヨ/イッヲ) | いよ |
| 名称 | 上古音 | 中古音 | 一般的な日本語表音 |
| 不弥国 | pɪuət-miĕr(プミェ) | pɪuət-miĕ(プミェ) | フミ国 |
| 投馬国 | dug-măg(ドゥマ) | dəu-mă(mbă)(ドゥマ) | トウマ国 |
| 弥弥 | miĕr-miĕr(ミェミェ) | miĕ-miĕ(ミェミェ) | みみ |
| 弥弥那利 | miĕr-miĕr-nar-lɪed(ミェミェナリ) | miĕ-miĕ-na((nda))-lɪi(ミェミェナリィ) | みみなり |
| 邪馬壱国 | ŋiăg-măg-・iet(ンィァマイッ) | (yiă)ziă-mă(mbă)-iĕt(ィァマイッ/ジィァマイッ) | ヤマタイ国/ヤマイチ国 |
| 伊声耆 | ・iər-thieŋ-gier(イシェンギェ) | ɪi-ʃɪɛŋ-gii(ィィションギィ) | イセイキ |
| 名称 | 上古音 | 中古音 | 一般的な日本語表音 |
| 倭 | ・uar(ゥァ) | ・ua(ゥァ) | わ |
| 狗邪韓国 | kug-ŋiăg(yiă)-ɦan(クンィァゥァン) | kəu-(yiă)ziă-ɦan(コゥィァゥァン/コゥジィァゥァン/) | コヤカン国 |
| 卑狗 | pieg-kug(ピェク) | piĕ-kəu(ピェコゥ) | ひこ |
| 卑奴母離 | pieg-nag-muəg-lɪar(ピェナムァリァ) | piĕ-no(ndo)-məu(mbəu)-lɪĕ(ピェノモリェ) | ひなもり |
| 爾支 | nier-kieg(ニェキェ) | niĕ(riĕ)-tʃɪĕ(ニェシェ,ニェチェ) | にき/にし |
| 𣳘謨觚 | siat-mag-kuag(シァマクァ) | siɛt-mo(mbo)-ko(シェモコ) | せもこ? |
| 柄渠觚 | pɪăŋ-gɪag-kuag(ピァンギァクァ) | pɪʌŋ-gɪo-ko(ピァンギォコ) | へここ? |
| 奴国 | nag(ナ) | no(ndo)(ノ) | ナ国/ヌ国 |
| 兕馬觚 | ?-măg-kuag(?マクァ) | zii-mă(mbă)-ko(ジィマコ) | しまこ |
| 多模 | tar-mag(タマ) | ta-mo(mbo)(タモ) | タモ |
| 伊支馬 | ・iər-kieg-măg(イキェマ) | ɪi-tʃɪĕ-mă(mbă)(ィィシェマ,ィィチェマ) | いしま |
| 弥馬升 | miĕr-măg-thiəŋ(ミェマション) | miĕ-mă(mbă)-ʃɪəŋ(ミェマション) | みましょう |
| 弥馬獲支 | miĕr-măg-ɦuăk-kieg(ミェマゥァッキェ) | miĕ-mă(mbă)-ɦuɛk-tʃɪĕ(ミェマゥェシェ,ミェマゥェチェ) | みまかくき |
| 奴佳鞮 | nag-keg-?(ナケ?) | no(ndo)-kai-?(ノカイ?) | なかてい |
| 狗奴国 | kug-nag(クナ) | kəu-no(ndo)(コゥノ) | クナ国 |
| 持衰 | dɪəg-sïuər(ディシゥァ) | ḍɪei-ṣïuei(ディシゥェィ) | ジスイ |
| 噫 | ・ɪəg(ィァ) | ʌi(アイ) | はい |
| 難升米 | nan-thiəŋ-mer(ナンシァンメ) | nan(ndan)-ʃɪəŋ-mei(mbei)(ナンシァンメイ) | なしめ/ナンショウマイ |
| 掖邪拘 | diak-ŋiăg-kɪug(ディァッキンィァキゥ) | yiɛk-(yiă)ziă-kɪu(ィェッジィァキゥ/ィェッキィァキゥ) | エキヤコ |
| 掖邪狗 | diak-ŋiăg-kug(ディァッキンィァク) | yiɛk-(yiă)ziă-kəu(ィェッジィァク/ィェッキィァコゥ) | エキヤコ |
| 載斯烏越 | tsəg-sieg-・ag-ɦuɪat(ツァシワウィァッ) | tsəi-sie-・o-ɦɪuʌt(ツァィシォヲッ) | サイシウエツ? |