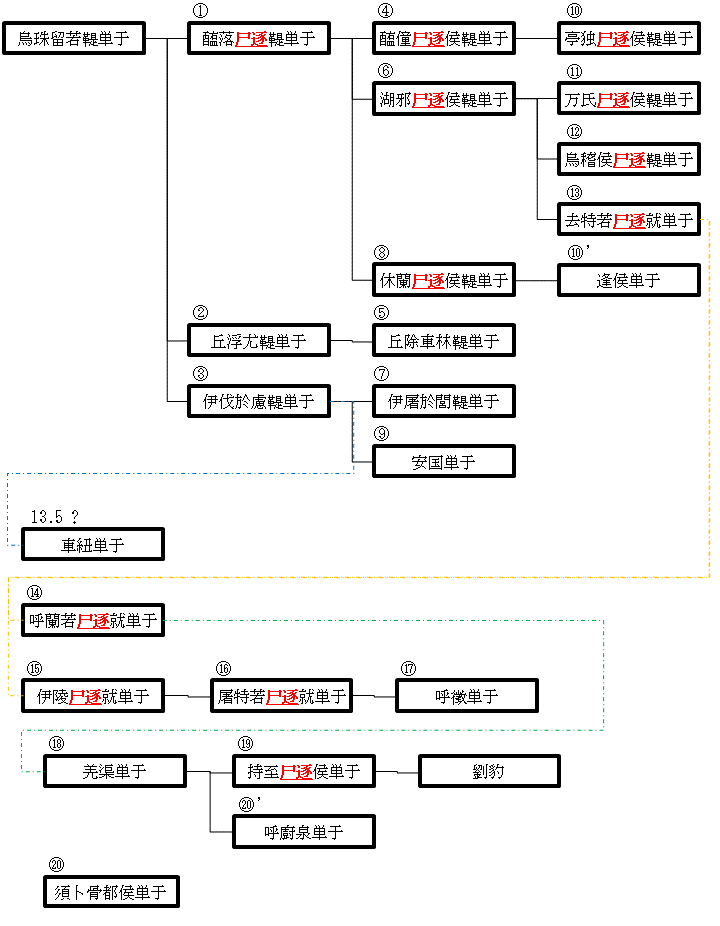1. 金印の読み方は正しいか
福岡市博物館には [漢委奴國王] の金印が保管されている らしい
一時期は一般公開されていて、画像も博物館の Webサイトで閲覧が可能で あったが流石に もう見る事は出来なくなっている
以下の画像は Wikipedia で公開されているものである
漢委奴国王 金印 - Wikipedia

漢委奴国王 印文 - Wikipedia

これも また日本史の教科書には必ずと言って良い程最初の方に載っている事で、金印の写真を見た人も多いと思う
どちらかと言うと、印を下から見た写真よりも印文の方を見た記憶の方が、印象が強いかも知れない
印を下から見ても黄金準純金の上、印書に反写して使用するために左右逆に彫金されているため、文字を読み取りにくいと言う事は ある
通説定説では、この金印文の読み方は
[漢_委_奴國王] (かんの わの なの こくおう)
等と言う三段
細切読法が
罷り通って読まれて しまっている
印の受領者は倭国の中に あった奴国の王で あると言う
だが、この読み方は本当に正しいので あろうか?
2. 印
漢委奴国王と刻された金印は、以下の通りで ある
印文 : 漢委奴國王
鈕 : 蛇鈕
鈕文様 : 魚子鏨
更に詳しい事は、以下を参照
漢委奴国王印 - Wikipedia
3. 関連文献 原文
.1 漢委奴国王
【後漢書】 卷八十五(一百十五) 列傳卷七十五 東夷傳 倭
撰者 : 南朝劉氏宋朝 范曄
建武中元二年 倭奴國奉貢朝賀 使人自稱大夫 倭國之極南界也 光武賜以印綬
.2 新匈奴単于章
【漢書】 卷九十四下 匈奴傳 第六十四下
撰者 : 東漢朝 班 固, 班 昭, 馬 続 等
王莽之篡位也 建國元年 遣五威將王駿率,甄阜,王颯,陳饒,帛敞,丁業六人 多齎金帛 重遺單于 諭曉以受命代漢狀 因易單于故印
故印文曰 匈奴單于璽 莽更曰 新匈奴單于章
明日 單于果遣右骨都侯當白將率曰
漢賜單于印 言璽不言章 又無漢字 諸王已下乃有漢言章 今印去璽加新 與臣下無別 願得故印
將率示以故印 謂曰
新室順天制作 故印隨將率所自為破壞 單于宜奉天命 奉新室之制
當還白 單于知已無可奈何 又多得賂遺 即遣弟右賢王輿奉馬牛隨將率入謝 因上書求故印
4. 伝承
細石神社 と言う神社が ある
古くは 佐々禮石神社 と表記されていたと言う
所在は 福岡県 糸島市 と ある
細石神社 - Wikipedia
現糸島市(旧前原市)三雲
南小路遺跡の拝殿で あった らしい
これは古田さん曰く、君が代 に登場するの 細石 の事で あろうと思う との事だ
この 細石神社 には、
漢委奴国王 の金印が宝物として伝わっていたが江戸時代に外部に流出したとの伝承が ある
細石神社の伝承
# この記述は現在は削除されている
この神社の近くに、伊都国王墓(最後の王墓らしい) と言われている
井原鑓溝遺跡 が ある
# 尤も、その地は伊都国では なく奴国では ないかと思うが
発見時から この金印は
"井原鑓溝遺跡 から出土したもので その際に窃盗された物で ある" との風評が流れていたらしい
あるいは、井原鑓溝遺跡 で発見されて 細石神社 に宝物として奉納されたが、その後それを聞き付けた者が盗み出した と言う可能性も考えられる
5. 印文読解
定説では、[漢_委_奴國王] と読む
しかしながら、
一分国に金印を与えるものか どうか、疑問が残る
やはり これは [漢_
委奴國王] と読むのが至当と思う
参照すべきは やはり中国での例と なるが、新 王莽 時代に匈奴に与えた印 [新匈奴単于章] が格好の例と なると思う
単于章置換と金印紫綬は共に光武帝在世時に行われた事で あり、同時代事件と言って良い
比べて みれば綺麗に対比して いるのが一目瞭然で あろう
章字もしくは璽字が省かれているのは、匈奴と漢使(原因は王莽) の間で起きた悶着を考慮したためかと思われる
新 匈奴 単于章
漢 委奴 國王
また、
委奴は後漢書に おける
倭奴の減画略字と見做すのが自然で あろう
付け加えるならば、当時の倭が
倭奴と呼称されていた可能性も あるかと思う
なお、
委奴国なる分国が実在したと主張する人も いるが、その場合、
委奴と
倭奴は不等と言う事なので あろうか
あるいは、以下の
【後漢書】 卷八十五(一百十五) 列傳卷七十五 東夷傳 倭
建武中元二年 倭奴國奉貢朝賀 使人自稱大夫 倭國之極南界也 光武賜以印綬
倭奴は誤記で
委奴が正しいとでも言うので あろうか
まるで理解し難いもので ある
6. 各印参照
以下で璽印検索が可能
羅福頤主编《秦漢魏晉南北朝官印徵存》檢索表 - 古代玺印鉴藏交流 - 玺印 押章 封泥 简牍 - 盛世收藏论坛 玉器,瓷器,书画,青铜,雕塑,造像,文玩,钱币,军品_中国最大艺术收藏鉴赏社区_盛世收藏网
7. A_奴 の語
委奴の様に何らかの語に奴字が接尾する形態の用例は、実は
委奴以外にも以下の様な ものが ある
.1 倭奴
当然の事で あるが、以下の例は
倭奴=日本の意で使用されている
a) 孟子舶載船覆溺説
孟子 の思想は日本には そぐわないので、日本に 孟子 を持ち込もうと すると載せた船が転覆沈没する と言う俗説が
五雑組と言う書に書かれている
五雑組とは 5部を
雑えた組紐の意らしい
【五雑組】 卷四 地部二
撰者 : 明代 謝 肇淛
倭奴亦重儒書 信仏法 凡中[註]経書皆以重価之購 独無孟子 云有攜其書往者 舟輒覆溺 此一奇事也
註:
国字 が脱落か
書は以下で公開されている
五雜俎:-中國哲學書電子化計劃維基
上田秋成 雨月物語 にも関連する記述あり
b) 隣交徴書
論語の東夷(恐らく倭)や漢書等の頃と倭と元代の日本を比べ、倭寇を念頭に記述しているらしい
【隣交徴書】 二篇卷一 論倭
著者 : 元代 呉莱
今之倭奴 非昔之倭奴也
昔雖到弱 猶敢拒中国之兵
況今之恃険 且十此者乎
郷自慶元 航海而来 艨艟数千 戈矛剣戟 莫不畢具 銛鋒淬鍔 天下無利鉄
出其重貨 公然貿易 即不満所欲 燔炳城郭 抄掠居民 海道之兵 猝無以応
.2 高麗奴
委奴や倭奴以外に A_奴 の型式で使用されている貴重な用例で ある
民族差別意識丸出し なので読んで不愉快に なる者も いるかもしれないが、
高麗奴 の語が続けて 3度も現われている
熾天使書城----舊唐書
【舊唐書】 列傳第五十四 高仙芝傳
撰者 : 後晋朝 劉昫,張昭遠,賈緯,趙瑩 等
仙軍還至河西 夫蒙靈察都不使人迎勞 罵仙芝曰
啖狗腸高麗奴 啖狗屎高麗奴 於闐使誰與汝奏得
仙芝曰
中丞
焉耆鎮守使誰邊得
曰 中丞
安西副都護使誰邊得
曰 中丞
安西都知兵馬使誰邊得
曰 中丞
靈察曰
此既皆我所奏 安得不待我處分懸奏捷書 據高麗奴此罪 合當斬 但緣新立大功 不欲處置
高麗人の腸料理(ホルモン焼や もつ鍋) を評して このような民族差別の言を発したものと思う
8. 漢匈奴悪適尸逐王印
とある方々は言う、漢匈奴
悪適尸逐王印を [漢_匈奴_
悪適_
尸逐王] と読み三段の
名号読法の例が存在する、と
しかしながら
悪適尸逐王は匈奴の王号で あり二段の名号読法が適用される
また、この印は銅印なので、直接比較して良いか疑問が残る
尸逐の字句が南匈奴から見受けられる様に なるので、これは南匈奴の王で あると思われる
悪適が部族名で ある
等と言う何等 根拠無き主張も あるが、これは南匈奴の単于号を見れば
容易に否定出来る
南匈奴単于号
| 単于号 |
出自 |
族群名等 |
| 烏珠留若鞮単于 |
分裂前の単于 |
屠各種族 攣鞮氏族 |
| 醢落尸逐鞮単于 |
烏珠留若鞮単于の子
以降南匈奴単于 |
屠各種族 攣鞮氏族 |
| 丘浮尤鞮単于 |
烏珠留若鞮単于の子
醢落尸逐鞮単于の弟 |
屠各種族 攣鞮氏族 |
| 伊伐於慮鞮単于 |
烏珠留若鞮単于の子
丘浮尤鞮単于の弟 |
屠各種族 攣鞮氏族 |
| 醢僮尸逐侯鞮単于 |
醢落尸逐鞮単于の子 |
屠各種族 攣鞮氏族 |
| 丘除車林鞮単于 |
丘浮尤鞮単于の子 |
屠各種族 攣鞮氏族 |
| 湖邪尸逐侯鞮単于 |
醢落尸逐鞮単于の子
醢僮尸逐侯鞮単于の弟 |
屠各種族 攣鞮氏族 |
| 伊屠於閭鞮単于 |
伊伐於慮鞮単于の子 |
屠各種族 攣鞮氏族 |
| 休蘭尸逐侯鞮単于 |
醢落尸逐鞮単于の子 |
屠各種族 攣鞮氏族 |
| 安国単于 |
伊伐於慮鞮単于の子
伊屠於閭鞮単于の弟 |
屠各種族 攣鞮氏族 |
| 亭独尸逐侯鞮単于 |
醢僮尸逐侯鞮単于の子 |
屠各種族 攣鞮氏族 |
| 逢侯単于 |
休蘭尸逐侯鞮単于の子 |
屠各種族 攣鞮氏族 |
| 万氏尸逐侯鞮単于 |
湖邪尸逐侯鞮単于の子 |
屠各種族 攣鞮氏族 |
| 烏稽侯尸逐鞮単于 |
湖邪尸逐侯鞮単于の子
万氏尸逐侯鞮単于の弟 |
屠各種族 攣鞮氏族 |
| 去特若尸逐就単于 |
湖邪尸逐侯鞮単于の子
烏稽侯尸逐鞮単于の弟 |
屠各種族 攣鞮氏族 |
| 車紐単于 |
不明 |
不明
屠各種族の呼衍氏,蘭氏,須卜氏,丘林氏の何れか と思うが どうか? |
| 呼蘭若尸逐就単于 |
不明 |
屠各種族 攣鞮氏族 |
| 伊陵尸逐就単于 |
不明 |
屠各種族 攣鞮氏族 |
| 屠特若尸逐就単于 |
伊陵尸逐就単于の子 |
屠各種族 攣鞮氏族 |
| 呼徵単于 |
屠特若尸逐就単于の子 |
屠各種族 攣鞮氏族 |
| 羌渠単于 |
不明
呼徵単于の縁戚か? |
一見すると羌渠種族と関連が ありそうでは あるが、
史料では屠各種族と読み取れる
呼衍氏,蘭氏,須卜氏,丘林氏の何れか と思うが どうか? |
| 持至尸逐侯単于 |
羌渠単于の子
劉豹の父 |
史料では屠各種族と読み取れる
呼衍氏,蘭氏,須卜氏,丘林氏の何れか と思うが どうか? |
| 須卜骨都侯単于 |
不明
須卜氏族の骨都侯が共立 |
屠各種族 須卜氏族
須卜骨都侯は正式な単于号で あるか不明[註] |
| 呼廚泉単于 |
持至尸逐侯単于の子 |
史料では屠各種族と読み取れる
呼衍氏,蘭氏,須卜氏,丘林氏の何れか と思うが どうか? |
註:
須卜骨都侯単于 とは 須卜氏 の骨都侯が共立された単于で あった事に由来している異常な単于号で あるが、何故か この単于の名は伝わっていない
当時の東漢朝は王朝として末期状態の混乱期に入っていたため記録が散逸したのか、それとも他国の事情に関わっている余裕が無かったのか は不明
あるいは、東漢朝は正式な単于とは認めて おらず正式な単于号が あったにも拘わらず敢えて無視して記録せず、須卜骨都侯単于 と言う便宜的な呼称を東漢朝側で名付けて こちらのみ記録した可能性も ある
A_尸逐_B と言う単于が意外と存在している事が分かる
単于は常に
攣鞮氏(後漢書では 虚連題氏 と記す) による世襲が前提と されており、王莽 が立てた単于や黄巾の乱後の混乱期を除き基本的には全て親子兄弟相続で あるので、全て同一種族
且つ同一氏族に属している
同一の種族氏族と言う事は、
即ち とある方々言う所の部族に ついても、当然の事ながら同じ部族と言う事に なる
系図を書くと以下の通りと なる
丸数字は単于の即位順を示すが、車紐単于 の扱い が難しく一応 13.5 と した
黒実線は続柄が明らかな系図で あるが、破線各色は私見に より判断して引いた
より
相応しい続柄系統の案を持たれている方からの識見を乞う
興味深いのは、
A_尸逐 が親子兄弟で連続して発生している事で あろうか
これは想像では あるが、
悪適尸逐王は
A_尸逐 系統の単于に近い存在(単于の子兄弟)で あったのかも知れない
少なくとも言える事は、
A_尸逐 の A は部族名では無く、
単于号や王号と言った称号の一部と見做さざるを得ないと言う事で ある
他には、匈奴の四貴種と呼称される氏族として 呼衍氏,蘭氏,須蔔(須卜)氏,丘林氏 が おり、匈奴の高位の存在は 攣鞮氏 もしくは この四氏族から挙げられた
高位者と言う事は、王も含むもの と思われる
つまり、
悪適尸逐王 は 攣鞮氏 か、攣鞮氏 で ないので あれば 呼衍氏,蘭氏,須卜氏,丘林氏 の何れか に属している可能性が高いと思われるので あり、
悪適部族等と言う
訳の分からない部族の一員とは考えにくい のである
また当然の事で あるが、文献史料上
悪適部族等と言うものの存在は一切確認出来ないので、悪適部族なる語は
想像上の観念に過ぎない
上記により、ここで以下の法則を提唱したい
A_尸逐 と ある場合、A_尸逐 は称号で ある
なお、匈奴四貴種の 須卜氏 は 攣鞮氏 の
姻族に して 王 昭君 の血統一族で あると思われる
王 昭君 と 復株累若鞮単于 の娘
云 は 伊墨居次(須卜居次) と名を伝えられ、須卜当 と婚姻する
伊墨居次 は 匈奴名で あろうか?
王昭君 - Wikipedia
匈奴は 王莽 の幼稚な原理主義に引っ掻き回される事に なるが、この際に 須卜居次 が歴史舞台に強制的に登場させられる事に なる
【漢書】 卷九十九上 王莽傳 第六十九上
莽念中國已平 唯四夷未有異 乃遣使者繼黃金,幣,帛 重賂匈奴單于 使上書言
聞中國譏二名 故名囊知牙斯今更名知 慕從聖制
又遣王昭君女須卜居次入待
9. 魏志倭人伝の奴国と伊都国
もう一つの判断材料として、魏志倭人伝 を添えよう
【三國志】 卷三十 魏志 烏丸鮮卑東夷傳 第三十 倭人傳
撰者 : 西晉(晋)朝 陳壽(寿)
漢時有朝見者 今使譯所通三十國
始度一海千餘里 至對海國 其大官曰卑狗 副曰卑奴母離 所居絶島 方可四百餘里 土地山險 多深林 道路如禽鹿徑 有千餘戸 無良田 食海物自活 乘船南北市糴
又南渡一海千餘里 名曰瀚海 至一大國 官亦曰卑狗 副曰卑奴母離 方可三百里 多竹木叢林 有三千許家差有田地 耕田猶不足食 亦南北市糴
又渡一海千餘里 至末盧國 有四千餘戸 濱山海居 草木茂盛 行不見前人 好捕魚鰒 水無深淺 皆沈沒取之
東南陸行五百里 到伊都國 官曰爾支 副曰𣳘謨觚,柄渠觚 有千餘戸 世有王 皆統屬女王國 郡使往來常所駐
東南至奴國百里 官曰兕馬觚 副曰卑奴母離 有二萬餘戸
東行至不彌國百里 官曰多模 副曰卑奴母離 有千餘家
南至投馬國水行二十日 官曰彌彌 副曰彌彌那利 可五萬餘戸
南至邪馬壹國 女王之所都 水行十日 陸行一月 官有伊支馬 次曰彌馬升 次曰彌馬獲支 次曰奴佳鞮 可七萬餘戸
お分かりで あろうか?
先ず見るべき所は、
漢時有朝見者 今使譯所通三十國
で ある
これは、東漢 光武帝 の時の奉献と金印 印綬を指している
にも拘わらず、その金印を印綬した国の事を、倭人伝では触れていない と言う事に なる
もし 奴国 が印綬の対象国で あれば、何かしら書き
留めるのが自然では ないか?
東南至奴國百里 官曰兕馬觚 副曰卑奴母離 有二萬餘戸
これを見る限り、抑々(そもそも) 奴国 には 王 すら存在しない
寧(むし)ろ王が いるのは 伊都国 の方で ある
東南陸行五百里 到伊都國 官曰爾支 副曰𣳘謨觚,柄渠觚 有千餘戸 世有王 皆統屬女王國 郡使往來常所駐
私は これに より、金印を下賜されたのは 伊都国王の先祖で あろうと解したので ある
伊都国は倭奴国が禅譲したのか
10. 漢委奴国王 印と奴国に関連性は無い
漢匈奴
悪適尸逐王印 が三段細切読法としては成立しない事が、上記に より判明した
よって、この金印文は [漢_委_奴國王] とは読めない
つまり、[漢_委奴國王] が正しいと言う事に なる
そう、
漢委奴国王印 は 奴国 に下賜された金印では無い ので ある
11. 関連 URI
参考と なる URI は以下の通り
金印 | 福岡市博物館
公開 : 2014年1月27日