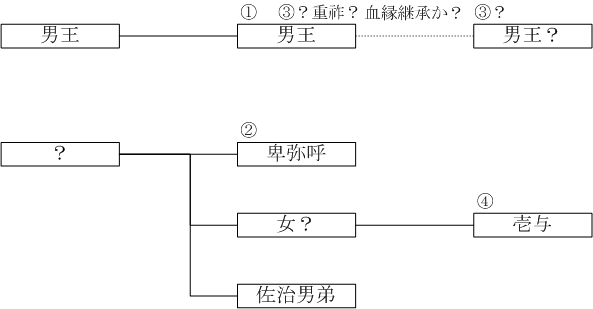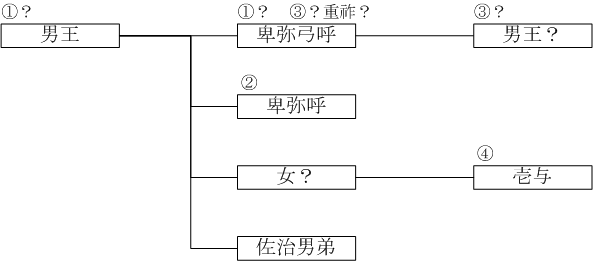1. 卑弥呼と卑弥弓呼は似ている…
長年、三国志 魏志倭人伝 の女王 卑弥呼 と 狗奴国 の男王 卑弥弓呼 の名前が似ている事に疑問を感じていた
そして、ふと思い付いたので ある
そう、卑弥呼 と 卑弥弓呼 の間柄は、実は兄妹(
若しくは姉弟) では なかったか
さもなくば、叔母甥の続柄では ないか
2. 倭人伝に見る記述
卑弥呼 と 卑弥弓呼 に関する記述は、やはり 三国志 魏志 倭人伝 を措(お)いて他には あるまい
フォトライブラリー | 弥生ミュージアム 三国志 魏志 倭人伝
【三國志】 卷三十 魏志 烏丸鮮卑東夷傳 第三十 倭人傳
撰者 : 西晉(晋)朝 陳壽(寿)
南至邪馬壹國 女王之所都 水行十日 陸行一月 官有伊支馬 次曰彌馬升 次曰彌馬獲支 次曰奴佳鞮 可七萬餘戸
自女王國以北 其戸,數道里可得略載 其餘旁國遠絶 不可得詳
次有斯馬國 次有已百支國 次有伊邪國 次有郡支國 次有彌奴國 次有好古都國 次有不呼國 次有姐奴國 次有對蘇國 次有蘇奴國 次有呼邑國 次有華奴蘇奴國 次有鬼國 次有爲吾國 次有鬼奴國 次有邪馬國 次有躬臣國 次有巴利國 次有支惟國 次有烏奴國 次有奴國 此女王境界所盡
其南有狗奴國 男子爲王 其官有狗古智卑狗 不屬女王
其國本亦以男子爲王 住七,八十年 倭國亂 相攻伐歴年
乃共立一女子爲王 名曰卑彌呼 事鬼道 能惑衆 年已長大 無夫壻 有男弟 佐治國
自爲王以來 少有見者 以婢千人自侍 唯有男子一人給飮食 傳辭出入
居處宮室樓觀 城柵嚴設 常有人持兵守衞
女王國東渡海千餘里 復有國 皆倭種
又有侏儒國在其南 人長三,四尺 去女王四千餘里
又有裸國 黒齒國復在其東南 船行一年可至
參問倭地 絶在海中洲㠀之上 或絶或連 周旋可五千餘里
其八年 太守王頎到官
倭女王卑彌呼與狗奴國男王卑彌弓呼素不和 遣倭載斯烏越等詣郡 説相攻擊狀
遣塞曹掾史張政等因齎詔書 黄憧 拜假難升米爲檄告喻之
卑彌呼以死 大作冢 徑百餘歩 徇葬者奴婢百餘人
更立男王 國中不服 更相誅殺 當時殺千餘人
復立卑彌呼宗女壹與 年十三爲王 國中遂定
政等以檄告喻壹與
壹與遣倭大夫率善中郎將掖邪狗等二十人送政等還 因詣臺獻上 男女生口三十人 貢白珠五千孔 靑大句珠二枚 異文雜錦二十匹
因(ちな)みに、卑弥呼の正式名は 俾弥呼 で ある
【三國志】 卷四 魏志 三少帝紀 第四 齊王芳
四年 春 正月 帝加元服 賜群臣各有差
夏 四月 乙卯 立皇后甄氏 大赦
五月 朔 日有食之既
秋 七月 詔祀 故 大司馬曹真 曹休 征南大將軍夏侯尚 太常桓階 司空陳群 太傅鍾繇 車騎將軍張郃 左將軍徐晃 前將軍張遼 右將軍樂進 太尉華歆 司徒王朗 驃騎將軍曹洪 征西將軍夏侯淵 後將軍朱靈 文聘 執金吾臧霸 破虜將軍李典 立義將軍龐德 武猛校尉典韋 於太祖廟庭
冬 十二月 倭國女王俾彌呼 遣使奉獻
上記四年は正始四年(西暦243年) を指す
卑弥弓呼の名も、
或いは 俾弥弓呼 で あったかも知れない
この二人の表音(発音) で あるが、一応以下の通り らしい
卑弥呼 の上古音は pieg-miĕr-hag、中古音は piĕ-miĕ-ho
卑弥弓呼 の上古音は pieg-miĕr-kɪuəŋ-hag、中古音は piĕ-miĕ-kɪuŋ-ho
ただし、これを どのように表音すれば良いのかは何とも良く分からないが、敢えて書き表すと すれば
上古音で あれば 卑弥呼 は ピミェハ、卑弥弓呼 は ピミェキゥンハ か
中古音と すれば 卑弥呼 は ピミェホ(ピミェフォ)、卑弥弓呼 は ピミェキゥンホ(ピミェキゥンフォ) もしくは ピミェキゥンウォ か
3. 倭王家の想定系図と王位継嗣闘争の可能性
.1 男弟佐治
卑弥呼 と 卑弥弓呼 に触れる前に、まずは 卑弥呼 の男弟に ついて考察して おきたい
そもそも 卑弥呼 の男弟とは、どの
様な出自なので あろうか
名前が伝えられて いないので、この人物を どの様に書き記せば良いか、もどかしい
佐治男弟と称するべきか、或いは いっその事 男弟サジ とでも名前を付けて しまおうか
煩わしいので、ここに
"佐治男弟" の語を用いる事を提唱したい
この佐治男弟、当然の事ながら その直後の
唯有男子一人給飮食 傳辭出入
の男子とは別人で あろう
それは それで、この男子が何者で あるのか、気に なる所では あるが、良く分からない
考察を戻すが、
有男弟 佐治國
と あるので、倭国国政の中枢に関与していたと言う事に なる
卑弥呼 との役割分担の内訳は不明では あるが、行政実務全般を総攬する役目に あったので あろう
倭人伝 の記述では、何となく姉の七光で政治に参画していた様に捉えられ兼ねないが、恐らくは非常に優秀で、実務処理能力に優れていたのでは ないかと考える
もし政治的に無能で あれば、倭国の内乱沈静後の政情を落ち着かせる事は難しいと思う
となると考えられるのは、この佐治男弟は識字階級の教養人で あったと言う事か
また、卑弥呼 と政治に参画しているので、身分上血縁上は 卑弥呼 と同等程度の身分、恐らくは倭国の支配階級に属していたものと思われる
いや、持って回った言い回しは
止そう
端的に言って、佐治男弟は王族で あろう
姉の七光で政治に参画していたのでは なく、始めから国政の中枢に いた人物で あったからこそ抜擢されたので あろうかと思う
或いは逆に、佐治男弟の行政手腕が買われて まず執政を委任され、その
伝手で卑弥呼が後から女王に推戴共立されたのかも知れない
佐治男弟の身分は王族と仮定したと して、それでは何故佐治男弟は王位に就けず、女性の 卑弥呼 が王位に就いたのか
一つには、まだ弥生の時代は女性上位社会で あった可能性の ある縄文時代の名残が残っていて、女性王位が後の世に比べて受容され易かったのでは ないか
次に考えられる事としては、卑弥呼 は王位継承の資格が あって佐治男弟には王位継承権が無いか、若しくは序列が低かったため、卑弥呼を差し置いて王位に就く事は難しかったと言う事かも知れない
となると血縁に ついても それなりに予測が可能と なろう
考えられる解は一つ、卑弥呼 は嫡腹長女で、佐治男弟は妾腹庶流で あったので あろう
つまり、卑弥呼 と佐治男弟は異母姉弟で あり、側妾の子は王位継承の序列が嫡出子よりも低いため倭国王には なれなかったものと思われる
.2 王位継承
次に女王国の王位継承に ついて述べる
其國本亦以男子爲王 住七,八十年 倭國亂 相攻伐歴年
乃共立一女子爲王 名曰卑彌呼 事鬼道 能惑衆 年已長大 無夫壻 有男弟 佐治國
本亦と言うのが何を指すのか良く分からないが、男王が複数代続いて その後に 卑弥呼が 共立されたと言う事か
卑彌呼以死 大作冢 徑百餘歩 徇葬者奴婢百餘人
更立男王 國中不服 更相誅殺 當時殺千餘人
復立卑彌呼宗女壹與 年十三爲王 國中遂定
卑弥呼 が崩御して後に男王が嗣いだと言う
しかし政情は安定せず、結局 卑弥呼 の縁者と思われる少女を再び女王として推戴した所、
漸く にして収束したと言う
なお、当然の事ながら 壱与 は佐治男弟の縁者でも あるが、佐治男弟の息女とは記述されていない
壱与 は 卑弥呼 宗女と あり佐治男弟宗女とは記述されていないため、血縁者としての立場は男弟よりも上なので あろう
となると考えられるのは、卑弥呼 の下の兄弟で且つ佐治男弟の上の兄弟、それが壱与の親と言う事に なる
しかしながら、佐治男弟の上に男子が いると なると何故その者を差し置いて佐治していたかと言う事に なるので、本来は行政に参画する事が難しい身分、つまり女性で あったと言う事か
となれば、壱与 の母は 卑弥呼 の妹で佐治男弟の姉と言う事に なろうか
これらの場合の王位継承順は、以下の通りと なる
この男王に ついては、幾つか候補が想定される
まず、卑弥呼 の先代の男王と同一人物で あった可能性が あろう
先王が王位に返り咲くと言う事態は あり得たかも知れない
年齢的に難しいかも知れないが、或いは先王の王太子が いた かも知れず、これならば可能性は充分と言えよう
これらの場合の王位継承順は、以下の通りと なる
次に、佐治男弟が 卑弥呼 の後を嗣いで践祚したと言う事も、可能性は低いが、あり得るで あろう
これらの場合の王位継承順は、以下の通りと なる
そして もう一つ、いや二つ可能性が ある
それは、狗奴国 が女王国を制して王位を奪う(狗奴国王兼邪馬壱国王と なる)か、或いは女王国を併合(邪馬壱国は一時的に消滅か) した場合に生じ易く なる事態で ある
つまり、卑弥呼 の次代男王と 卑弥弓呼 が同一人物と言う事に なる
もっとも、卑弥弓呼 が 卑弥呼 の後を嗣いだので あれば倭人伝にも何らかの記述として反映されて然るべきかも知れないので、可能性は低いのかも しれない
となると もう一つの可能性は、卑弥弓呼 の王太子が王位を嗣いだのでは ないかと言う事だ
これらの場合の王位継承順は、以下の通りと なる
そして最後、本考察の
見処と なるが、
卑弥呼と卑弥弓呼が兄妹で あったと仮定した場合、どうなるか
卑弥弓呼 が嫡長子で あった場合、こうなる
上記の分派型で あるが、卑弥弓呼 が嫡男、ややこしいが第二子で且つ長男で あった場合の王位継承順は、以下の通りと なる
更に二つ上の系図の分派型、
佐治男弟が実は 卑弥呼 の義弟、妹の夫で壱与の父親で あったと仮定した場合の王位継承順は、以下の通りと なる
これ ならば、何故佐治男弟が 卑弥呼 の後継王者と ならずに 壱与 が跡を継いだのか、非常に明解で ある
佐治男弟には王位継承権が始めから無かったと言う
訳で ある
いや、それでも尚即位を強行したため臣民の反感を買い、退位せざるを得なくなって壱与に譲位した可能性も、あるかも知れないか
.3 女王国と狗奴国は大きく異なる国家で あったのか
狗奴国 と女王国に ついて、人種や言語、宗教や政治形態等で大きく差違が ある様に捉える人を見受ける
九州説で あれば熊曽(熊襲) や薩摩隼人等に見立てる者が いて、関西説では東国の毛野勢力や東北の蝦夷に見立てる者も いる
しかしながら、女王国と 狗奴国 は政治形態としては似通ったもので あったのでは ないかと思われる
例えば、
南至邪馬壹國 女王之所都 水行十日 陸行一月 官有伊支馬 次曰彌馬升 次曰彌馬獲支 次曰奴佳鞮 可七萬餘戸
女王の下に官が置かれている事が分かる
一方狗奴国にも、
其南有狗奴國 男子爲王 其官有狗古智卑狗 不屬女王
とあり、身分制度や階級層の区分が確立している事を窺わせる
王の名が近い事からも、恐らくは言語も共通で あったものと思われる
地理風土に おいても、
次有斯馬國 次有已百支國 次有伊邪國 次有郡支國 次有彌奴國 次有好古都國 次有不呼國 次有姐奴國 次有對蘇國 次有蘇奴國 次有呼邑國 次有華奴蘇奴國 次有鬼國 次有爲吾國 次有鬼奴國 次有邪馬國 次有躬臣國 次有巴利國 次有支惟國 次有烏奴國 次有奴國 此女王境界所盡
其南有狗奴國 男子爲王 其官有狗古智卑狗 不屬女王
女王に属する奴国と境界を接している地に 狗奴国 が ある様にも思える
勿論、これだけでは 奴国 と 狗奴国 が地続きか どうか までは分からないが、仮に狗奴国が女王国に属する国家で あったとしても特に違和感の無さそうな描写で ある
人種面その他で女王国と差違が ある様に見えるのは、以下の地域で あろう
女王國東渡海千餘里 復有國 皆倭種
又有侏儒國在其南 人長三,四尺 去女王四千餘里
又有裸國,黒齒國復在其東南 船行一年可至
東に海を隔てた地に、人種面で倭人と同じ様に見える国が あると言う事だ
その南にも国が あり、どうやら人種が異なるらしい
この地形描写を考慮すると関西説では適合しにくいと思われるが、九州説で あれば中国地方と四国地方として符合しよう
或いは 侏儒国 は倭種の国の南では なく、女王国の南かも知れない
それならば 侏儒国 は南九州、鹿児島か宮崎と言う事に なろう
東の倭種の国は女王に属していないと言う点から推し量るに、人種言語は女王国と共通ながら政治形態は別と言う事か
侏儒国 は人種が異なるので あろう
断言は出来ないが、恐らくは東の倭種の国は出雲勢力で、侏儒国 とは弥生人よりも身長が低い縄文人の遺存聚落で あったのでは ないかと思うが どうか
何れにしても考えられる事と しては、女王国と 狗奴国 には大きく異なる国では無いで あろう と言う事で ある
.4 卑弥呼と卑弥弓呼は何故不和で あったのか
卑弥呼と卑弥弓呼の不和と交戦の状況が、少しだけ書き残されている
倭女王卑彌呼與狗奴國男王卑彌弓呼素不和 遣倭載斯烏越等詣郡 説相攻擊狀
不和の理由は不明で あるが、戦闘状態を招いてまで争う事なので あろうか
王者同士が思う事が あったとしても、国家間で相互に無視して交流を断てば、動乱に及ぶ必要は無いのでは ないか
相い攻撃すると言う文言を四角四面に訳せば、両国が相互に攻勢を取り合っている状況、と言う事に なろうか
つまり一方が一方的に攻め込んで他方が専守防衛していると言う事では なく、卑弥呼の側からも卑弥弓呼に対して攻勢を仕掛けていると言う事で あろう
そこまでして何故互いに争ったので あろうか
これに対する一つの解としては、両者が女王国の王位継承を争う近親憎悪を抱き、果てし無き骨肉の争いを演じざるを得なかったのでは あるまいか
二人が嫡出の同母兄弟で、王位継承に敗れた 卑弥弓呼 が女王国を脱出亡命し、女王国の勢力圏を逃れて新たに国を興したのが狗奴国では なかったか
.5 卑弥呼は一般名称か
以上が本考察で あるが、ここで一つ触れて おきたい
卑弥呼 の語は人名では なく、役職等の単なる一般名称で ある等と主張する者が いる様で ある
しかしながら、魏朝への奉献時の奏文には 卑弥呼 の自署名が記名されて いたものと思われるので、実名で あろう
卑弥呼 が一般名詞で その後の 壱与 が人名と言うのは、不自然で ある
また、稀に言霊思想に より諱を他人に伝える筈が無い云々等と物申す者も いるらしいが、当時の中国では諱で あろうと書くべき箇所には諱を記していた筈なので、その後の日本の習慣を三世紀の古代日本に遡及して適用すべきでは ないと思うので あるが、どうで あろうか
.6 卑弥呼は巫女で あったか、それとも巫女に されたのか
最後に、一つの私見を述べて おきたい
突拍子も無い案に思われるかも知れないが、卑弥呼 は自由意志で巫女に なったのでは無く、
強制的に巫女に させられたのでは無いか
誰に?
それは 卑弥呼 の父親で あったと思われる
男王で ある
これは想像の域を出ないが、例えば父王に長女子 卑弥呼 と次子 王太子が いたが、王位争奪の懸念を感じて卑弥呼を巫女と して しまい、王太子に
継嗣せしめよう と
図ったのかも知れない
何やら後代の仏教寺院に尼僧として出家すると言う状況が思い浮かぶが、それに近いのかも知れない
当時は
未だ倭国に仏教は伝来していなかったと思われるので、出家とは つまり
尼さんでは無く巫女で あったと言う可能性は ある
父王と しても、兄弟で王権を奪い合う事態に なるよりは、どちらか一方を政治権力から遠避けて おいて王位継承候補者から除外して おきたかったと言うのは、親の心情としては充分に理解出来る
或いは こうして 卑弥呼 は世俗から引き離されて人里離れた山奥に でも
籠もらされたのか…
.7 倭と壱与は西晋朝に登場しなくなるのは何故か
壱与は西晋朝に一度だけ登場するが、その後は登場しなくなってしまう
理由は分からないが、交戦していた狗奴国との戦闘が終息したのであろうか
卑弥呼と卑弥弓呼は不仲で あったらしいが、壱与と卑弥弓呼は和睦出来たのかも知れない
狗奴国との和平が実現すると西晋朝を恃む必要が無くなってしまい、それで姿を消したと言う事は考えられる
人は目の前に解決すべき問題が無い場合、好んで自身より大きな存在を頼らないものである
4. 関連 URI
参考と なる URI は以下の通り
卑弥呼 - Wikipedia
卑弥弓呼 - Wikipedia
公開 : 2014年4月14日