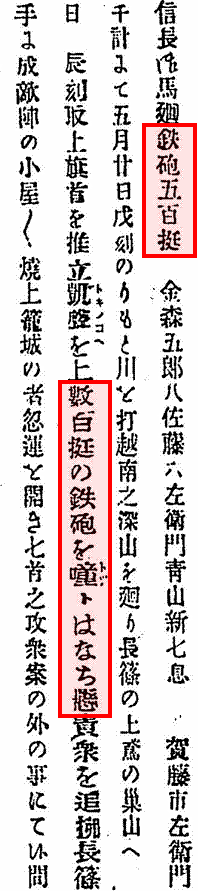1. 火縄銃の音で馬が暴れ出したと言う主張
井沢氏は著書で、長篠の戦いでは織田勢が用意した火縄銃の発砲音が轟いて銃声に不慣れな武田勢の馬が暴れ出し、それが長篠の戦いの帰趨を決したものと主張している
本当で あろうか?
2. 考察
.1 武田勢は銃声を聞いた事が無かったのか
それでは井沢氏の主張の是非を考察する
先(ま)ず、氏の著書を引用しよう
【逆説の日本史】 9 戦国野望編 P.435
長篠の合戦において、織田軍の鉄砲の弾丸は、実は一発も命中しなくてもいいんです。
なぜなら、火縄銃の轟音だけで馬は暴れ出し、ちょうど竹崎季長の馬のように乗り手を振り落とそうとしますから。
火縄銃の音を聞いたことがありますか。
私はあります。
耳をつんざく轟音とはまさにこのことです。
それが三千挺も集まって火を吹いたら、それだけで日本の歴史が始まって以来、まさに前代未聞の轟音が設楽原に轟いたはずです。
もちろん武田軍というのは、前にも述べたように純然たる騎兵ではなく歩兵も混じっていますが、その中核は騎兵です。
それがまったく機能しなくなる。
あとはまさに狙い撃ちということです。
この箇所は、仲々(なかなか)に あくどい論の進め方を している
ここで鉄炮
[註1]数を
三千挺で あると
しれっと書いているが、
当人は三千挺も鉄炮が あったとは考えていない様で ある
にも拘(かか)わらず
この時点で否定せず、この主張の後で
さらっと否定しているのは何故かと言えば、
"鉄炮数は三千挺で ある" と言う先入観を読者に抱(いだ)かせて おいた方が、自説の展論に都合が良いからで あろう
逆に言うと、鉄炮の実数が千挺と言う記述は この直後に置かれているが、論述を前後して
前に鉄炮数が千挺しか無かったと書いてしまうと、持論に都合が悪くなると言う事で ある
註1:
鉄炮の表記は鉄砲と書かれる事が多いが、意義上は鉄炮の方が正しいと考えるので、本考察では鉄炮の表記を採用する
【逆説の日本史】 9 戦国野望編 P.435
ところで、三段撃ちというのは虚構だという説があるが、私も実はこれには賛成だ。
当時の信長の経済力からいっても、せいぜい千挺がいいところだろう。
三千というのは、三段撃ちという虚構のために、千に三をかけたのではないか、実際はそんなことをしなくても千挺でも充分に馬防柵以上の抑止効果があったのだ。
現在の有力説は、
馬防柵を ある程度突破されたものと考える他無いと言う論に落ち着いていると思う
馬防柵内に斬り込まれたと言う事は、
騎馬が暴れ出さずに織田陣に突入した事を示している
つまり、織田勢の鉄炮射撃を以(もっ)て しても、
武田勢の馬は暴れる事は無かったと言う事に なる
更に言えば、
織田勢は鉄炮の一斉斉射を行って いないと言うのが、馬防柵の侵入同様、現在の有力説と なっている
例えば以下の書を引用しよう
【戦国の軍隊 現代軍事学から見た戦国大名の軍勢】
著者 : 西股 総生(にしまた ふさお)
第四章 足軽と長柄 P.103
■長篠の鉄炮三段撃ち
話をもとに戻そう。
戦国時代(おおむね一六世紀)の日本では、軍隊が等間隔で整然と隊列を組んで行動する習慣はなかった。
というより、そうした行動をとる必然性がなかった。
したがって、映画やドラマに出てくるように、鉄炮隊が一斉射撃を繰り返すことなどありえない。
この問題に早くから気付いていたのが藤本正行氏だ。
藤本氏は、史料の検証と論理的思考にもとづいて、長篠の合戦で織田・徳川連合軍が三千挺の鉄炮を一斉射撃して武田軍を撃破した、という通説をみごとに否定した。
藤本氏が、多数の鉄炮による一斉射撃はありえない、という所説をまとまった文章で発表したのは九〇年代に入ってからであるが(『信長の戦国軍事学』)、一般向けの雑誌記事などではもう少し早くから主張していたようだ。
小銃の一斉射撃という戦法が世界史的にはどのように成立したか、という問題を考えるならば、藤本氏の指摘は充分に首肯できる。
つまり、鉄炮千挺で あろうと
同時に発砲した訳では無いので、
日本の歴史始まって云々と言う程の轟音には なり得ない事、明瞭で あろう
ところで、井沢氏は織田の経済力から鉄炮数が千挺が せいぜい で あろうと主張しているが、その根拠を全く示していない
恐らく
特に根拠は無く、単に適当な事を言っているに過ぎないのでは無いかと思われる
実際に織田勢よりも鉄炮数を多く保有していたと思われる石山 本願寺や紀州 雑賀衆や紀州 根来衆は、織田の経済力を越えていたか どうかは何とも言えない
寧(むし)ろ紀伊国は海運業以外には特に産業と言えるものも見当たらずないので、経済力に おいて豊かで あったとは言えず、出稼ぎとして鉄炮傭兵と言う稼業を行っていた らしい
どうやら、経済力と鉄炮数には直接の相関関係は無い様に思える
それに、織田勢が保有する鉄炮総数は千挺よりも多かったと考えるのが妥当で あろう
当時の織田家は方々(ほうぼう) てに敵勢力と対峙して おり、各地の戦線から鉄炮を抽出して一箇所に集めた数が、千挺の鉄炮なので ある
織田家の鉄炮総数が千挺では無いので ある
こう言うと、井沢氏としては織田家の総数が千挺で あるとは書いていない等(など) と言い逃れを するのかも知れない所では あるが
【逆説の日本史】 9 戦国野望編 P.435
もう一つの不思議は、ではなぜ今までこんな簡単なことに誰も気がつかなかったかということであろう。
いやいや、
不思議と評されるべきで あるのは井沢氏の おかしな、或(ある)いは異常な頭だけで あろう
正常な人間は、井沢氏の様な嘘八百を滔々(とうとう)と吐露(とろ)しないもの なので ある
【逆説の日本史】 9 戦国野望編 P.437
もちろん戦国時代にもそういう訓練をした馬は、たとえば信長の軍の中にはいたかもしれない。
しかし、武田家はこれまで述べたように鉄砲の生産力においても硝石の輸入ルートにおいても、信長や西日本の大名にかなり劣る存在、つまり「鉄砲後進国」なのである。
信長軍にはできても、信玄軍には「馴し方」の訓練など物理的に不可能だ、ということである。
馬が銃声に過剰に反応しない様に するための馴(なら)し方に触れた後で、武田家では その訓練が不可能で ある等(など)と断じている
私は武田家に おける馬の訓練の状況と言うものは寡聞にして知らないので あるが、武田家にも相応の鉄炮が存在していたと言う事実は知っている
【戦国の軍隊 現代軍事学から見た戦国大名の軍勢】
第五章 鉄炮がもたらした革新 P.137
興味深いのは、『勝山記』(『妙法寺記』)の天文二十四年(一五五五)条に見える、次のような記載だ。
アサヒノ要害エモ、武田の晴信人数ヲ三千人、サケハリヲイルホドノ弓八百丁、テツハウヲ三百カラ入レ候、
「アサヒノ要害」とは、信濃善光寺平の北西に聳える旭山城という山城で、この時期、越後の長尾景虎(上杉謙信)と善光寺平の覇権を争っていた武田軍にとっては、重要な軍事拠点であった。
『勝山記』の記主は僧侶だから、合戦関係の記事は伝聞にもとづいているはずで、誇張や誤情報が含まれている可能性はある。
ただ、『勝山記』には川中島合戦に関する記事がかなり多く、内容も具体的で、川中島の戦況に関心をもって情報収集につとめていた様子も窺われるから、一概に作り話とは斥けにくい。
■旭山城の三〇〇挺
初伝から十余年をへて、鉄炮が西日本の戦場に普及しつつあった天文二四年(一五五五)の時点で、武田軍に三〇〇挺もの鉄炮があったとすれば、ちょっとした驚きだが、この話はどこまで信じて良いものだろうか。
実のところ、これまでも多くの研究者が『勝山記』の記事を疑問符つきで引用してきているが、筆者は充分にありえる話だと思う。
まず、当時の善光寺平をめぐる戦況の中で、旭山城は武田軍にとって決定的に重要な拠点であった。
『勝山記』の伝える三〇〇〇という守備兵力は、城の重要度から見ても城の規模から見ても、妥当な数字と言えそうだ。
面白いことに戦国大名たちは、戦略的に非常に重要な城には、三〇〇〇~四〇〇〇の兵力を入れて守備させるのが通例となっていたようで、これは戦国の比較的早い時期から最後まで、あまり変わっていない。
たとえば、天文一五年(一五四六)におきた河越夜戦は、後北条軍の籠もる河越城を山内上杉・扇谷上杉・古河公方の連合軍が攻囲し、北条氏康がこれを急襲撃破した戦いだが、このとき河越城を守っていた人数について、氏康自身が「三千余」と書状に記している。
第一章で紹介した山中城の場合も、松田康長・北条氏勝以下の守備兵は四〇〇〇余であったが、秀吉の侵攻に備えていた後北条氏側の重要拠点は、おおむね二五〇〇~四〇〇〇程度の兵力で守備している。
どうやら、大名たちの間には三〇〇〇~四〇〇〇の守備兵があれば、大概の城は守り通せるという共通認識があったのだろう。
問題は鉄炮の数だが、『勝山記』の記事に多くの研究者が違和感を覚えるのは、旭山城という前線の城一つに三〇〇挺の鉄炮を送り込めるのだとしたら、武田軍全体ではものすごい数の鉄炮を保有していたことになるのではないか、という忖度をしてしまうからではないだろうか。
では、弓八〇〇、鉄炮三〇〇というのが多少大きめのラフな数字だとしても、一〇〇挺単位の鉄炮が当時、武田軍の保有する全量だったとしたら、どうだろう。
天文二四年の時点で、武田軍は善光寺平以北を除く信濃をほぼ制圧していたし、相模の北条氏康、駿河の今川義元とは同盟関係にあって、戦略の焦点は川中島方面に絞られていた。
だとしたら、信玄が大金を投入してまとまった数の鉄炮を買い付け、その新兵器をもっとも重要な戦略拠点に投入するのは、むしろ理に叶った措置と言えるのではなかろうか。
おそらくこの鉄炮隊は信玄直属で、足軽部隊だった可能性が高いものと思う。
そして、最前線において新兵器の有効性が実証された結果、永禄に入る頃から信玄は一般の家臣にも、鉄炮の調達・装備を指示するようになっていった、と考えればつじつまが合う。
私も西股氏の見解に同意する
日本の歴史研究家は平和
惚けして しまって軍事には疎(うと)く、時に軍事に関して拒否反応すら示す者が多過ぎるので ある
恐らく三百挺の鉄炮は武田勢の大部で あって、それを意識的に実戦投入を行っていたものと思う
つまり、
1555年の時点で既に武田氏には三百挺の鉄炮を保有し実戦で使用していると言う事で あり、武田勢の騎馬は この時点で鉄炮の銃声と言うものを充分に聞き知っていたので ある
確かに武田家は鉄炮後進国では あるかも知れないが、しかし
鉄炮の銃声を聞いた事が無いと言う事は、当然ありえないので ある
どうして井沢氏は こう言う
明白な事実を無視し、或いは捏造するので あろうか
全く以て理解に苦しむ次第で ある
【逆説の日本史】 9 戦国野望編 P.437
おわかり頂けただろうか。
天才の業績をさぐることは、かくも困難なのである。
充分に分かった
何が?
井沢氏の頭が異常で、正常な状態に恢復(かいふく)せしめるのは頗(すこぶ)る困難で あろうと言う事が
.2 鳶ヶ巣山 奇襲に鉄炮五百挺を投入
長篠 設楽ヶ原 での戦いの
直前に、徳川勢が
鳶ヶ巣山砦を奇襲し奪取している
この時、徳川勢は織田勢から
鉄炮五百挺を貸与され、これを戦場に投入している
しかも、この時の五月二十一日 辰の刻、
数百挺の鉄炮を一斉斉射した らしき描写が見える
引用しよう
【信長公記】 卷中 卷之八 三州長篠御合戰之事
著者 : 太田 牛一
今度間近く寄(よせ)合(わせ)候事與天(天の与(あた)うる)所(に)候間悉く被討果(討ち果たさる)の旨 信長被廻(御案を廻(めぐ)らされ)御身方一人も不破損(破損せざる)候樣に被加御賢意(御賢意を加えられ) 坂(酒の誤か)井左衛門尉 被召寄(召し寄せられ) 家康御人數の内弓鉄砲可然(然るべき)仁を召列(めしつれ) 坂井左衛門尉大將として二千ばかり、左衛門尉大将として二千計(ばかり)幷(ならび)に信長御馬廻鉄砲五百挺 金森五朗八佐藤六左衛門靑山新七息 賀藤市左衛門爲御檢使(御検使と為(し)て)被相添(相(あ)い添えられ)都合四千計(ばかり)にて五月廿日戌刻のりもと川を打越(し)南之深山を廻り長篠の上鳶の巣山へ五月廿一日 辰刻取上旗首を推立(て)凱聲を上數百挺の鉄砲を噇ト(どっと)はなち(=放ち)懸(け)責衆(=攻め衆)を追拂(追い払い)長篠の城へ入(り)城中之者と一手に成(なり)敵陣の小屋〱[註2]燒上(げ)籠城の者忽運を開き七首之攻衆案の外の事にて候間致癈忘(癈忘(はいもう)致し)風來而(かぜきたって)(=鳳来寺の誤か)さして敗北也
註2:
和文縦書き時の繰り返し符号(踊り字)の一種で "くの字点"
"小屋小屋" と読む
国立国会図書館にて公開されている以下を画像で、直接確認する事が出来る
近代デジタルライブラリー - 信長公記. 巻之中:
ここから コマ番号6 と言う箇所に飛ぶと、長篠の戦いの記述部分の画像が表示される
分かり易くするため、上記から一部を抽出して以下に提示するので、一斉斉射と覚しき箇所を よくよく ご覧いただきたい
数百挺と五百挺とが同意なのか、五百挺よりも少なかったのか、それとも徳川勢の鉄炮を加えて五百挺よりも多かったのかは、この文章からでは分からないが、概(おおむ)ね五百挺程度の一斉斉射の銃声が轟(とどろ)いたので あろう
つまり、
設楽ヶ原の戦いの前に武田勢は鉄炮五百挺の銃声を聞いている訳で ある
この戦いの後に起きた設楽ヶ原での戦いで、武田勢の馬が銃声に驚くと言う事が、果たして起きるので あろうか?
理性的に考えれば、
既に五百挺の鉄炮の銃声を聞き知っているので、その直後に千挺の銃声を聞いた所で、格別驚くには当たらないと考えざるを得ないので あるが、如何(いかが)で あろうか
或いは、もし鳶ヶ巣山での奇襲時に武田勢が銃声に驚いて騎馬が機能しない事態が発生していたとしても、
武田勢とて馬鹿では無いので あるから、当然
何らかの対応策を用意するで あろう
設楽ヶ原の決戦は鳶ヶ巣山の奇襲よりも後に行われている訳(わけ)で、武田勢は銃声の対策が充分で無ければ設楽ヶ原の決戦を廻避するで あろう
にも拘わらず武田勢は設楽ヶ原の決戦に臨(のぞ)んだと言う事は、
鉄炮の銃声に対する何らかの術(すべ) を持ち合わせていたものと考えざるを得ないので ある
.3 画像考察
井沢氏は自説が正しいもので あると言う事を読者に印象付けようと する意図からか、著書でイラスト(絵)を掲載している
しかしながら、この
イラストの見せ方に ついて、私は とても
悪意を感じてしまう ので ある
先ず 【逆説の日本史】 9 戦国野望編 P.432 に 蒙古襲来絵詞 の画像を載(の)せている
構図としてはイラストの右下に、モンゴル軍の音響火器に驚く 竹崎 季長 と その乗馬が描写されている
このイラストは見開きページの右ページ、ページ上方から中段に かけて掲(かか)げられているので、恰度(ちょうど)
本を開くとページの右外側に来ていて、目立つ様に なっている
恐らく これは、
音に驚いた馬が竹崎 季長を振り落とそうとしている様子を、意図的に視覚に訴える構図と してページを構成したので あろう
実際の 蒙古襲来絵詞 の画像は以下の通りで ある
Wikipedia 蒙古襲来絵詞 (4334x1462)
良く見ると、井沢氏の著書に掲げられたイラストは
実際の画像から切り貼りして編集した形跡が見て取れる
上記画像と著書のイラストを見比べると一目瞭然で あるが、これは
竹崎 季長の乗馬を必要以上に浮き上がらせる様に仕上げられている事が見て取れる
次に井沢氏は次のページ、【逆説の日本史】 9 戦国野望編 P.433 に 長篠合戦図屏風 のイラストを載(の)せている
こちらの構図は、見開きページの左側、ページの右上にイラストが来る様に配置されている
製本に あたって本を閉じる側を ノド と言うが、イラストがノド側に あって、画像の左側には文章が三行 配置されている
所で私は この見開きページを見て、疑問に思った事が ある
それは、右ページの 蒙古襲来絵詞 のイラストに比べて左ページの
長篠合戦図屏風 のイラストの方が、明らかに小さいので ある
更に言えば、この
イラストがノド側に配置されていると言う事も留意すべきで あろう
活字本でも漫画本でも何でも良いが、身近に ある本で良いので、ある程度ページ数の ある本を開いて いただきたい
この時、読者の
目に留(と)まり易(やす)いのは見開きページの外側で、ページを閉じているノドに近い部分は読者の意識が薄くなる傾向が あると思うが、如何で あろうか
そう、井沢氏は意図的に、長篠合戦図屏風 の
イラストの右側を読者の目から隠そうとしている ので ある
では何を隠そうとして いるのか?
答えは簡単、長篠合戦図屏風 の
右側に描写されている武田勢の馬を隠そうとしている ので あろう
こちらも、長篠合戦図屏風 の実際の画像を見て いただこう
Wikipedia 長篠合戦図屏風 六曲一隻 (1654x773)
この画像を良く見ると(いや、
良く見なくても一目瞭然で あるが)、井沢氏の著書に掲げられたイラストは
実際の画像から徳川勢と鉄炮隊の箇所のみを切り取ってイラストと している事が分かる
このイラストの右側には本来は武田勢が書かれていて然(しか)るべきなので あるが、この右側部分は井沢氏の所論に とって
都合が悪いので、敢えてイラストから除外し、そして除外した事を読者に意識させない様にページ構図を仕組んだので あろう
と言う事で、上記画像を表示させ、
目を皿の様にして よくよく 武田勢の馬を ご覧いただきたい
銃声に驚いて騎手を振り落とそうと している武田勢の馬は、果たして存在するで あろうか?
いや存在しない、一頭たりとも見当たらない、全く皆目全然いないので ある
これは一体どう言う事で あろうか?
そう、
長篠合戦図屏風 には銃声に驚いている武田勢の馬は一頭も書かれて いない ので ある
これは つまり、長篠合戦(設楽ヶ原 合戦) では、
銃声に驚いた武田勢の騎馬は全然いなかった、と言う事を示している
少し上で 長篠合戦図屏風 のイラストが 蒙古襲来絵詞 のイラストよりも小さいと書いたが、これは 長篠合戦図屏風 の右側に書かれていた武田勢を見せたくないために除外したため、
イラストの横幅が狭く小さく なって しまった事が原因で あろう
3. 結論
上記考察から導き出される結論は以下の通りで ある
1) 武田勢は少なくとも三百挺以上の鉄炮を保有しており、鉄炮の銃声を充分に聞き知っていたものと思われる
2) 長篠合戦(設楽ヶ原合戦)で投入された鉄炮は三千挺では無く千挺で ある
3) 設楽ヶ原合戦では鉄炮の一斉斉射は行われて おらず、銃声は個別に轟いていたが日本史初まって以来の轟音と言う程では無かった
4) 設楽ヶ原合戦の直前に鳶ヶ巣山奇襲が行われており、そこで五百挺の鉄炮に よる一斉斉射が行われたものと思われ、武田勢は五百挺の銃声と言う轟音を経験して おり、銃声に よる轟音は対策済で あったものと思われる
5) 長篠合戦図屏風 を見る限り、銃声に驚いて騎手を振り落とそうとしている武田勢の騎馬は見当たらない
と言う訳で、井沢氏の著書に ある、長篠の戦いでは火縄銃の発砲音が轟いて武田勢の馬が暴れ出し、これが長篠の戦いの帰趨を決したと言う主張は、完全に間違いで あると言う事が分かる
これで また一つ、井沢氏が嘘八百の与太論説を徒(いたず)らに垂れ流していると言う事を明らかと する事が出来たと言えよう
4. 関連 URI
参考と なる URI は以下の通り
蒙古襲来絵詞 - Wikipedia
長篠の戦い - Wikipedia
公開 : 2014年10月13日