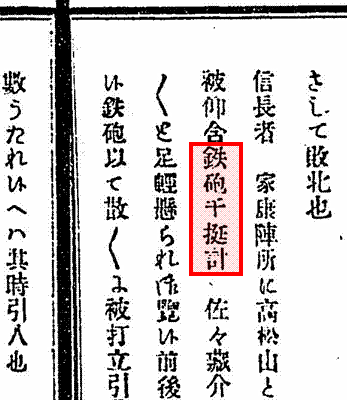1. 通説に疑義あり
日本史の教科書には必ずと言っていい程載っている以下の長篠合戦での鉄炮
[註1]三段射撃は とても有名で、通説定説では用意した鉄炮数は三千挺と言われている
武田軍の騎馬隊を防ぐ為に馬防柵を作り、その後ろに鉄炮隊を配置したと言う
長篠合戦図屏風 六曲一隻(ろっきょくいっせき)
しかしながら この通説には疑義が持たれて おり、私も通説は虚構で あろうと考える
註1:
鉄炮の表記は鉄砲と書かれる事が多いが、意義上は鉄炮の方が正しいと考えるので、本考察では鉄炮の表記を採用する
2. 参考文献
長篠合戦を知る上で参考と なる文献は以下の通り
信長公記(原文) 町田本
信長公記 巻八
3. 戦役名
一般的には "長篠の戦い" と呼ばれている
しかしながら、実は長篠から かなり離れている
様だ
正しくは 設楽原(したらがはら) 合戦 か 長篠設楽原合戦 と言うべきで あろう
4. 鉄炮数
【信長記】 池田本(池田家文庫所蔵) では
"鉄砲千丁" の横に "三" と書き込まれて おり、この三字は他字よりも小さいため、恐らくは著者では ない別人に より後から追記されたものと思われる
【信長公記】 (太田 牛一 著) では、"
鉄砲千挺計" と ある
いずれも鉄炮数は
千挺と伝えて おり、
三千挺では無い
文献は文字を追うだけで無く、実際に目視して確認した方が良い
信長公記 に ついては国立国会図書館にて公開されている画像が あるので、直接以下を参照されたい
近代デジタルライブラリー - 信長公記. 巻之中:
ここから コマ番号6 と言う箇所に飛ぶと、当該の画像が表示される
表示を分かり易くするため、上記画像から一部を抽出して以下に
掲げるので、目を
凝らして ご覧いただきたい
【信長公記】 卷中 卷之八 三州長篠御合戰之事
信長者 家康陣所に高松山とて小高き山御座侯に被取上敵の働を御覽し御下知次第可働の旨兼而より被仰含鉄砲千挺計 佐々藏介前田又左衛門野々村三十郎福富平左衛門塙九郎左衛門 御奉行として近〱[註2]と足輕(を)懸られ御覽(じ)侯前後より攻(め)られ御敵も人數を出し候一番
註2:
和文縦書き時の繰り返し符号(踊り字)の一種で "くの字点"
"近近" と読む
見ての通りで あるが、
鉄炮は千挺で ある と言う事が一目瞭然で ある
5. 実際の戦闘
実際の戦闘状況を把握するため、上図よりも大きな図を見て みよう
長篠合戦図屏風 六曲一隻 (1654x773)
長篠合戦屏風 - Google 検索
馬防柵の前に並ぶ鉄炮足軽が描かれている(馬防柵の後ろに並ぶ者も いる)
しかも 1列に並んで おり、3列に並んでいる様には見えない
これを見る限りに おいては、長篠合戦屏風が捏造なのか もしくは鉄炮三段射撃が虚構と言う事に なる
そして長篠合戦屏風と信長公記の記述は一致する個所を見出せる(以下 6. 長篠合戦屏風の信憑性 を参照) ため、かなり正確で あろうと思われる
やはり鉄炮三段射撃は虚構なのだ
6. 長篠合戦屏風の信憑性
長篠合戦屏風には信長所蔵の "二十四間総覆輪筋兜" が以下の様に描かれているので、実際に参加した者が いたか もしくは参加者から聞き出して書かれたのでは ないかと思う
伝・織田信長所用 二十四間総覆輪筋兜
信長公記 での記述と照らして見てても、
【信長公記 卷八 天正三年 町田本】
志多羅の郷は、一段地形くぼき所に侯
敵がたへ見えざる様に、段貼に御人数三万ばかり立て置かる
先陣は、国衆の事に侯の間、家康、たつみつ坂の上、高松山に陣を懸げ、滝川左近、羽柴藤吉郎 丹羽五郎左衛門両三人、あるみ原へ打ち上げ、武田四郎に打ち向ひ、東向きに備へらる
家康、滝川陣取りの前に馬防ぎの為め、柵を付けさせられ、彼のあるみ原は、左りは鳳来寺山より西へ太山つゞき、又、右は鳶の巣山より西へ打ち続きたる深山なり
先陣は徳川勢で高松山に布陣し、後ろに 滝川一益 勢が あるみ原? に布陣したと言う事か
史実として、徳川が先手で織田が後詰と言うのは充分に考えられる事なので、文献と屏風が正確に一致している様に思える
となれば上記 5. の長篠合戦屏風は正確で あると判断せざるを得ないので ある
7. 現在の主流説
現時点で主流と なっている説は鉄炮足軽が 3人一組と なって横に並び、順番に射撃する と言う考え方で ある
縦が駄目なら横並び、と言えば何となく
安直かも知れないが、まぁ そう言う事で ある らしい
いや、正確に真横に並んだ
訳では無く斜め後ろ方向(日本人で あれば恐らくは右斜め後ろ に並びたくなる か?)に隊列を組んだのかも知れないが
私は この手法に対して
三色信号機(点灯)射撃[註3]と言う呼称を提唱したい
註3:
信号機灯の点灯動作は実は世界的な取り決め が あるらしく、日本の道路信号機は標準から外れている らしい
確かに これならば道理に
適っている様に思える
8. 私見を幾つか
蛇足かも知れないが、更に私の個人的な見解を付しておきたい
馬防柵は騎馬の突進を防ぐため および鉄炮射撃時の射撃振れ を防ぐため と思われるが、と同時に もう一つの効果も発揮していたのでは無いか と考える
馬は本来は臆病と言うか慎重な動物なので、疾走を妨害する物の無い平原ならば大いに駆けるが障害物を見ると途端に尻込み し足踏み してしまう
そうなると もう乗馬した武者が いかに馬を進ませようと尻を叩いても しても
その場を動くまい
騎馬武者が馬防柵の目の前で停止しているので あれば鉄炮隊に とって
恰好の標的と化して しまうで あろう
そもそも当時の鉄炮は現代の銃器に比べて遥かに命中精度が悪い上に疾走している騎馬を銃撃しても中々 命中しなかったと思うが、動かない的で あれば話は別で ある
武田軍も事態を把握した後では何か対策
[註4]を講じたのかも知れないが、少なくとも開戦当初に限っては武田勢先鋒はなす
術無く潰滅してしまったのでは あるまいか
註4:
馬に目隠し を して尻を叩けば障害物が あっても突進する筈なので、武田勢も これで凌いだ可能性は ある
また、鉄炮射撃が始まると周辺には火薬の臭い が充満したか と思うが、これも馬は嫌うのでは無いか
私は馬を飼った事が無いので断言は出来ないが、恐らく火薬の臭いを避けようと すると思う
つまり、馬防柵と火薬で武田の騎馬隊は馬防柵の中に突っ込む事が出来ず に戦闘が終了してしまった可能性も あるか と思っている次第で ある
9. 結論
長篠合戦での
鉄炮三段射撃は虚構 で ある
用意した鉄炮数は三千挺と言われているが、これも虚構であり、実際には
千挺しか なかった
更に言えば、鉄炮隊は馬防柵の後ろに配置したと言うが これも虚構であり、実際には
馬防柵の前後に配置していた ものと思われる
10. 関連 URI
参考と なる URI は以下の通り
公益財団法人 犬山城白帝文庫|財団所有の文物
徳川美術館
公開 : 2014年1月9日